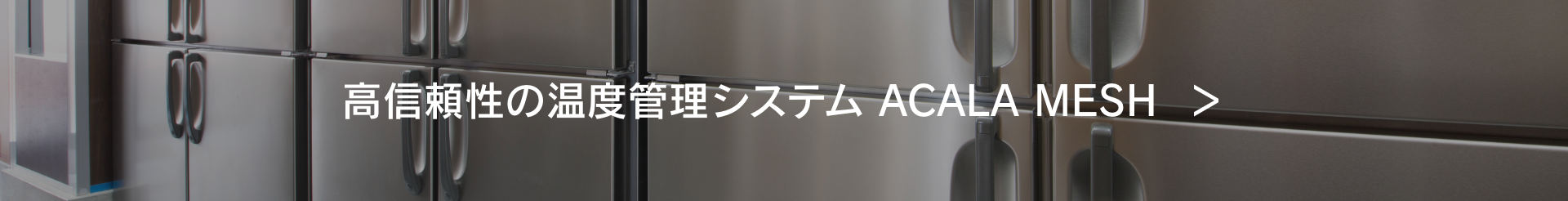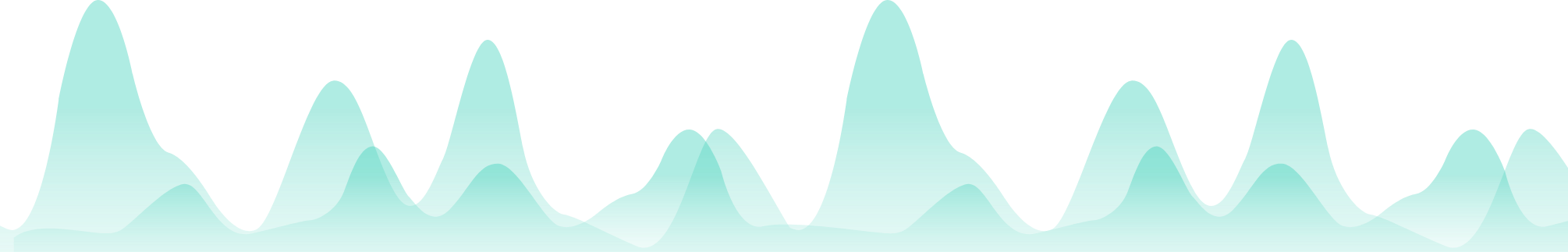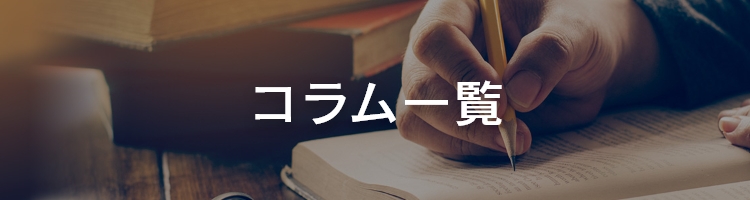
HACCP7原則12手順の覚え方!現場に導入するメリットと活用方法を紹介
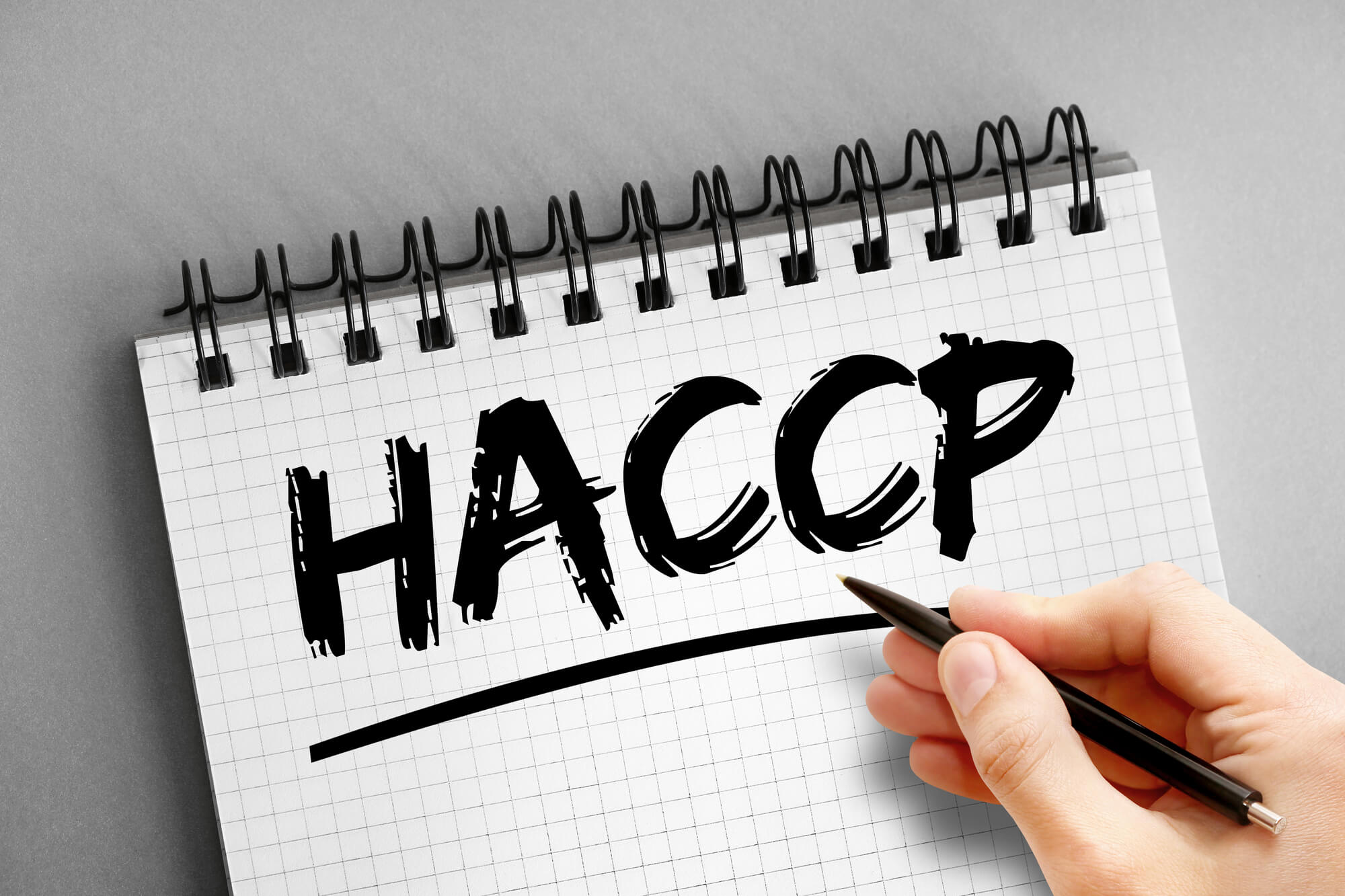
HACCPの7原則12手順の導入を検討しているけれど、「業務に追われてなかなか手が付けられない」「7原則12手順は複雑で、従業員にどう説明すればいいのかわからない…」といった悩みを抱えていませんか? 本記事では、専門用語だらけで難解に思えるHACCPの7原則12手順を、順を追って詳しく解説します。 さらに、得た知識を現場でどう活かすのか、現場に導入することでどのような変化が生まれるのかについてもご紹介します。安心安全な食を届けるための第一歩として、ぜひご一読ください。
HACCPとは?基本をわかりやすく解説
まずは、HACCPの基本について押さえておきましょう。
この章では、HACCPの概要として、食品業界で重要視されている理由について解説します。また、HACCPの2つの種類と取り組むべき基準も紹介するので、参考にしてみてください。
HACCPの概要|なぜ今、食品業界に必要とされているのか
HACCPとは、食品の安全性を製造工程の段階から確保するための国際的な衛生管理手法です。
従来の完成品を抜き打ち検査する方法とは異なり、食中毒などの健康被害を未然に防ぐことを目的としています。2021年6月からすべての食品等事業者に導入が義務化されました。
従来の方法では、すべての製品の安全性を100%保証することが困難でした。しかし、HACCPの義務化により、食品製造の全工程(原材料の受け入れから製造、出荷まで)において、どこで危害が発生しうるかを予測・分析でき、継続的な監視が可能になったのです。
HACCP導入により、問題のある製品が出荷されるリスクを根本から低減できることから、食品業界において重要視されています。
HACCPは2種類|コーデックスHACCPと簡略化HACCP
HACCPは、国際基準である「コーデックスHACCP」と、小規模事業者向けに基準が緩和された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(簡略化HACCP)」の2種類があります。自社の事業規模や業種によって、どちらに取り組むべきかが異なります。
■コーデックスHACCP(基準A)
| 対象 | 大規模事業者、と畜場、食鳥処理場など |
| 内容 | 7原則12手順に厳密に基づき、自社でHACCPプランを構築・実行する必要がある |
■HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(基準B/簡略化HACCP)
| 対象 | 従業員50人未満の小規模な事業者、店舗での小売販売のみの事業者など |
| 内容 | 各業界団体が作成した「手引書」を参考に、簡略化されたアプローチで衛生管理計画を作成・実行する |
まずは厚生労働省のWebサイトや、所属する業界団体の情報を確認し、自社がどちらの基準に該当するかを正確に把握しましょう。自社に合った基準を選ぶことが、HACCPをスムーズに導入するための重要なステップです。
HACCP7原則12手順を簡単に理解する

この章では、HACCPの土台となる「12手順」のプラン作成の流れ、重要とされる「7原則」の目的について解説します。
さらに、「7原則12手順」の各工程の内容もご紹介します。手順ごとに行う内容に沿って、理解しながら覚えることが大切です。
12手順|具体的なプラン作成の流れ
HACCPプランは、国際的に定められた「12の手順」に沿って作成します。
12の手順は、大きく分けて「準備段階の5手順(手順1~5)」と「HACCP計画を立てる7原則(手順6~12)」の2つのフェーズで構成されています。
手順1~5で土台を固めてから、核心部分である7原則(手順6~12)に取り組む流れになっており、この2つのステップを意識することで、より記憶に定着しやすくなります。
HACCP7原則とは|各原則の目的
HACCPの中核をなすのが、具体的な衛生管理ルールを定めた「7原則」です。7原則は、食品への健康危害(ハザード)を科学的根拠に基づいて管理するための、世界共通の考え方です。
7原則は、一連のPDCAサイクルで構成されており、サイクルを回すことで継続的に食品の安全レベルを向上させることを目的としています。
7原則を自社の製品や調理工程に当てはめて、「どこが危ないか」「どう管理するか」を具体的に考えることが大切です。
HACCP7原則12手順の覚え方
HACCPの7原則12手順は、単に言葉を暗記するのではなく、一連のストーリーとしての流れで理解するのが効果的な覚え方です。
■ステップ1:準備段階の5手順(手順1~5)
まず、HACCPプランを策定するための土台を作ります。「誰が、誰に、何を、どのように作るか」を明確にし、「それが現場と合っているか」を確認する流れで覚えましょう。
- 手順1:HACCPチームの編成
専門知識を持つメンバーでチームを作ります。
- 手順2:製品説明書の作成
製品の原材料、特性、保存方法などを文書にまとめます。
- 手順3:用途と消費者の確認
製品がどのように使われ、誰が食べるのかを明確にします。
- 手順4:製造工程一覧図の作成
原材料の受け入れから出荷まで、製造の流れを図にします。
- 手順5:製造工程の現場確認
作成した工程図が、実際の現場作業と一致しているかを検証します。
■ステップ2:HACCP計画を立てる7原則(手順6~12)
準備が整ったら、具体的な衛生管理計画を立てます。
「危険を見つけ、対策ポイントを絞り、ルールを決め、監視し、問題があれば直し、全体を見直し、すべてを記録する」というPDCAサイクルのような流れで覚えるのがポイントです。
- 手順6(原則1):危害要因の分析(HA)
各工程に潜む食中毒菌などの健康被害の危険性をリストアップします。
- 手順7(原則2):重要管理点(CCP)の決定
リストアップした危害要因を管理するために、特に重要な工程を決定します。
- 手順8(原則3):管理基準(CL)の設定
「温度〇℃以下」「加熱〇分以上」など、安全を確保するための具体的な数値を設定します。
- 手順9(原則4):監視(モニタリング)方法の設定
管理基準が守られているかを継続的にチェックする方法(誰が、いつ、どのように)を決めます。
- 手順10(原則5):改善措置の設定
モニタリングの結果、管理基準から外れた場合にどう対応する(製品の廃棄、原因究明など)か、あらかじめ決めておきます。
- 手順11(原則6):検証方法の設定
定めたHACCP計画全体が有効に機能しているか、定期的に評価・検証する方法を定めます。
- 手順12(原則7):記録の作成と保管
これまで決めた計画や、日々のモニタリング結果などをすべて文書化し、記録・保管します。
【HACCP7原則12手順】導入のメリットと現場での活用方法
HACCPを現場に導入することで多くのメリットが得られます。活用する際は、ポイントを押さえることが大切です。
この章では、HACCP導入によるメリット、HACCPプランをスムーズに作成・運用するための具体的なポイントから導入後の改善のコツまで、実践的な活用方法をご紹介します。
HACCP導入の3つの効果|現場に起きる変化とは
HACCP導入は、義務だからと消極的に取り組むものではありません。
企業に「安全性向上」「従業員の意識改革」「生産性向上」という3つの大きなメリットをもたらす価値ある投資です。
具体的には、以下のようなメリットが得られます。
- 安全性の向上:HACCPの導入・実践は、取引先や消費者に対して「食の安全に真摯に取り組んでいる」という明確な証拠になる。これにより、企業のブランドイメージや信頼性の向上が期待できる。
- 従業員の意識改革:各工程の重要性や目的が明確になるため、従業員一人ひとりが作業の必要性を理解して業務にあたるようになる。結果として、責任感や衛生管理への意識が高まる。
- 生産性の向上:衛生管理の手順が標準化されることで、作業効率が向上する。また、問題が発生した際も原因究明が容易になり、クレーム対応の迅速化や不良品の削減に繋がる。
HACCPは、場当たり的な衛生管理ではなく、科学的根拠に基づいた体系的な管理手法です。そのため、食の安全性が向上するのはもちろん、組織全体のレベルアップに繋がります。
HACCPプラン作成手順を成功させるポイント
HACCPプランを形骸化させず、現場で確実に運用するためには、次のポイントを押さえて取り組むことが大切です。
- 「現場目線」:計画を作るのは管理者でも、実行するのは現場の従業員。実際に作業する人の意見を積極的に取り入れることが大切。
- 「スモールスタート」:最初からすべての工程で完璧なプランを目指す必要はない。最も重要なCCP(重要管理点)から、運用を開始し、徐々に範囲を広げていくこと。
- 「ツールの活用」:日々の記録や管理の手間を削減できる管理ツールの導入も有効な選択肢のひとつで、プラン作成に役立つ。
理想ばかりを追い求めた完璧なプランは、現場の実態とズレが生じてしまい、結局使われなくなってしまいます。現場の従業員に合わせて着実に進められる現実的なアプローチが有効です。
HACCP導入後の検証方法と改善のコツ
HACCPは単なる計画書ではありません。効果を維持・向上させるためには、定期的な「検証」と、それに基づく「改善」の繰り返しが欠かせません。
検証方法の例として、内部監査や記録データの分析が挙げられます。
HACCPチームは定期的に、「計画書通りにモニタリングが実施・記録されているか」「是正措置は適切に行われたか」などについて、チェックリストに沿った確認が必要です。
記録データの分析に関しては、過去の温度記録を見返し、「基準値の逸脱傾向」のパターンを見つけ出して原因を探りましょう。
検証で見つかった問題点や従業員からの意見を取り入れ、HACCPプランそのものを見直します。
HACCPとは現場のPDCAサイクルそのものです。継続的な改善により、企業の衛生管理レベルは着実に向上していきます。
まとめ
本記事では、HACCP7原則12手順の目的と内容、導入のメリット、現場での活用方法をご紹介しました。複雑に見えるHACCPも、ポイントを押さえれば決して難しいものではありません。
HACCPにおける7原則12手順は、食の安心を守るためには不可欠です。現場に浸透させるためには、簡易ステップから始めて、現場に合った導入を進めていきましょう。
タイムマシーン株式会社の「ACLCA」のような温度の自動記録システムを活用すれば、蓄積された記録データの分析や管理が容易になり、効果的な改善活動を後押しします。ぜひ、検証と改善のサイクルのために、現場への導入をご検討ください。