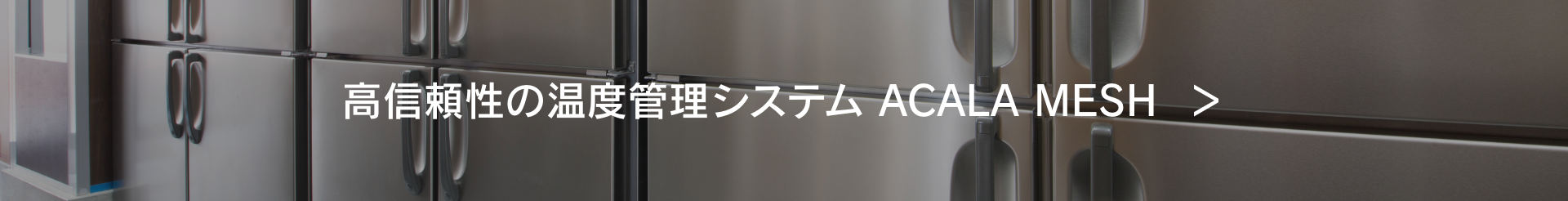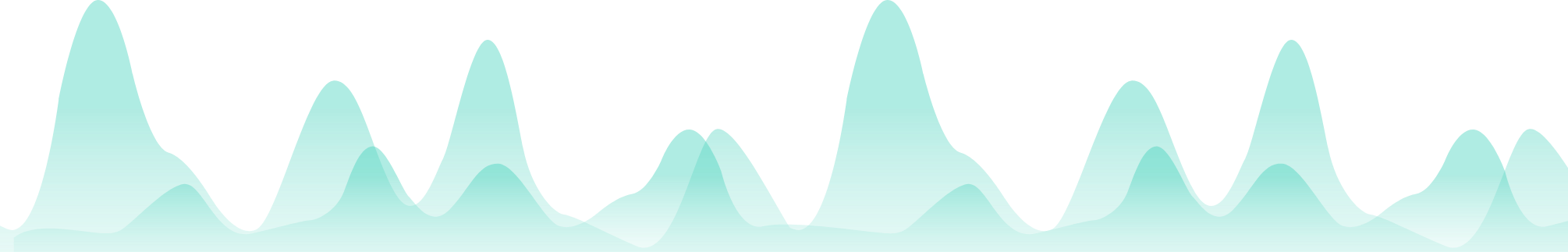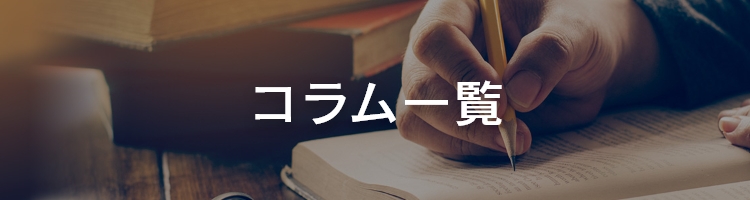
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理との違いは?7原則12手順も紹介

食品衛生法改正で義務化された「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、すべての食品事業者に関わる重要なルールです。これまでの管理やHACCPに基づいた衛生管理との違いは何なのでしょうか。 本記事では、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理との違いについて解説します。また、HACCPを実施するための「7原則12手順」や、HACCP導入におけるメリットもご紹介しますので、自社で実践すべきことを明確にするためにも、ご一読ください。
HACCPに基づいた衛生管理との違い
食品衛生法改正により、食品事業者全てにHACCPにおける衛生管理が義務付けられました。しかし、取り組むべき衛生基準は、事業者の規模などにより、2つに分類されています。
それが以下の2つです。
- HACCPに基づく衛生管理
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
それぞれの内容と違いについて見ていきましょう。
HACCPに基づく衛生管理
HACCPに基づく衛生管理とは、コーデックス委員会(CAC)(※)が策定したHACCPの7原則12手順に厳密に従って、衛生管理計画を作成し、実行していく方法です。
原材料の受け入れから製造、加工、出荷までの全ての工程において、食中毒の原因となる可能性のある危害要因を特定・分析し、その危害要因を除去または低減する上で重要な工程を定めます。そして、継続的にモニタリングし、記録を管理していく衛生管理システムです。
(※)コーデックス委員会とは、消費者の健康保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、FAO(国連食糧農業機関)及びWHO(世界保健機関)により設置された国際的な政府間機関。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理は、比較的小規模な事業者を対象とした基準です。具体的には、店舗での小売販売のみを行う事業者、飲食店やパン屋、従業員数が50人未満の食品製造・加工事業者などが該当します。
2つの基準の違い
2つの基準の違いは下表の通りです。
| 項目 | HACCPに基づく衛生管理 | HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 |
| 対象事業者 | 大規模事業者、と畜場、食鳥処理場、輸出を行う事業者など | 小規模事業者(飲食店、小売店、小規模な製造・加工業など) |
| 基準の厳格さ | コーデックスの7原則12手順に厳密に従う必要がある | HACCPの考え方を基本としつつ、簡略化した運用が可能 |
| 手順の具体性 | 自社で全ての工程について危害要因分析を行い、CCPを設定 | 業界団体作成の「手引書」を参考に、管理ポイントを設定・管理 |
| 記録の量・詳細さ | HACCPに関する専門的でより高度な知識 | 手引書を理解し、実践できれば対応可能 |
| 記録の量・詳細さ | より詳細で多くの記録が求められる | 手引書に示された範囲での記録が中心 |
事業者は、自社の規模や業態に応じて、どちらの基準で衛生管理に取り組むべきかを判断する必要があります。
基本的には、従業員数や事業内容によって区分されますが、判断に迷う場合は管轄の保健所や業界団体、専門家などに相談することをおすすめします。
HACCP実施のための7原則5手順

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を適切に実施するために、1993年にCodex(国際食品規格)委員会が策定した「7原則12手順」が策定されました。
食品の安全性を確保するための中核となるのがHACCP7原則です。HACCP7原則を適用する前に、5つの手順を実施する必要があります。5つの手順を実施することにより、HACCP7原則が効果的に適用されます。
・手順1:HACCPのチーム編成
専門知識を持つ担当者で構成し、それぞれの知見を持ち寄ることが大切です。
・手順2:製品説明書の作成
原材料や添加物、製品の特性などを詳細に記述した書類を作成します。のちの危害要因分析の基礎情報となります。
・手順3:意図する用途及び対象となる消費者の確認
製品がどのように消費されるか、対象消費者などを明確にし、注意すべき危害要因や管理方法を把握します。
・手順4:製造工程一覧図の作成
原材料の受け入れから製品の出荷までの全工程を作成します。危害要因が発生しうるか所の特定に繋がります。
・手順5:製造工程一覧図の現場確認
作成した工程図が実際の現場と一致しているか確認します。
〈手順1~5:原則1~7を進めるにあたっての準備〉
手順6~12では、準備段階で得られた情報をもとに、具体的に7つの原則を適用していきます。
・手順6 【原則1】:危害要因分析の実施(ハザード/HA)
各製造工程における危害要因を特定し、発生の可能性とリスクを評価し、措置を検討します。
・手順7 【原則2】:重要管理点(CCP)の決定
食品の安全性を確保する上で、継続的な監視や管理が必要なポイントを特定します。
・手順8 【原則3】:管理基準(CL)の設定
危害要因を許容範囲まで低減または除去するために守らなければならない基準値を設定します。
・手順9 【原則4】:モニタリング方法の設定
管理基準を逸脱していいないか継続的に監視します。
・手順10【原則5】:改善措置の設定
管理基準を逸脱した場合に、どのような改善措置を取るかを定めておきます。
・手順11 【原則6】:検証方法の設定
作成したHACCP計画が有効に機能しているか、計画通りに実施されているかを確認します。
・手順12 【原則7】:記録と保存方法の設定
HACCPの実施に関する全ての活動を正確に記録し、適切な保管方法を定めます。
HACCPの7原則12手順は、食品の安全性を確保するための科学的根拠に基づいた体系的なアプローチです。
手順1から順に丁寧に進めることで、自社の製造工程に潜む危害要因を特定し、効果的に管理するための具体的なプランを策定し、実行できます。
書類を作成するだけでなく、現場での実践と継続的な見直しや改善が伴うことで機能するシステムです。
準備段階である手順1~5で現状を正確に把握し、7原則の適用段階(手順6~12)で具体的な管理方法を定めて、確実に実行して記録し、さらに検証していくことが求められます。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を導入するメリット
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を導入することは、法の遵守だけでなく、事業者にとってさまざまなメリットがあります。ここでは、HACCPの導入や運用の目的を明確にし、衛生管理を継続的な維持に繋げましょう。
- 社員の衛生管理意識の向上
- 食品の安全性の確保
- 従業員教育のルール化
- 作業効率のアップ
- 食品事故の防止
- 万が一の際の自己防衛
上記のメリットは相互に関連し合っており、組織全体の品質管理レベルと生産性を向上させるポイントになります。
導入には初期コストや労力がかかる場合もありますが、長期的な視点で見れば、企業の信頼性の向上や市場価値の維持、競争力の強化に不可欠だと言えるでしょう。
大切なのは、システムの構築だけでなく、日常に落とし込み、確実に運用して、定期的に見直しと改善を続けることです。
まとめ
HACCPに基づく衛生管理とHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の違いは、事業者の規模に応じた衛生管理のレベルにあります。
「HACCPに基づく衛生管理」はより厳格な手順が求められますが、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は、小規模事業者でも取り組みやすいよう簡略化されているのが特徴です。しかし、食品の安全性を確保する目的は同じであり、その基礎には7原則12手順の考え方があります。
食の安全を守るために、HACCP導入におけるメリットを理解し、自社の状況に応じて衛生管理体制を構築することに着実に取り組みましょう。