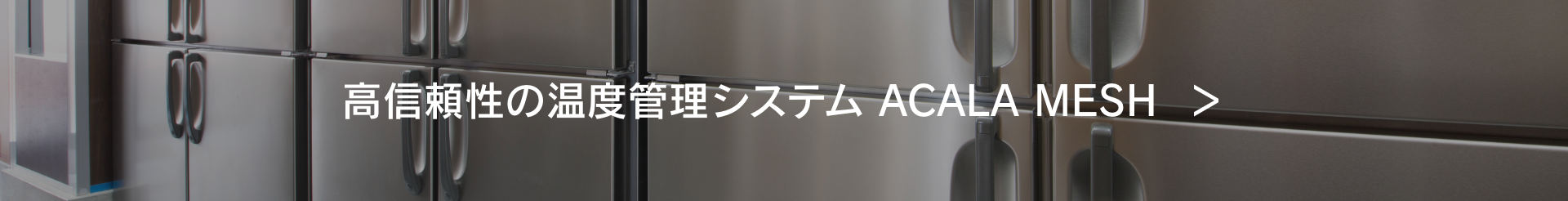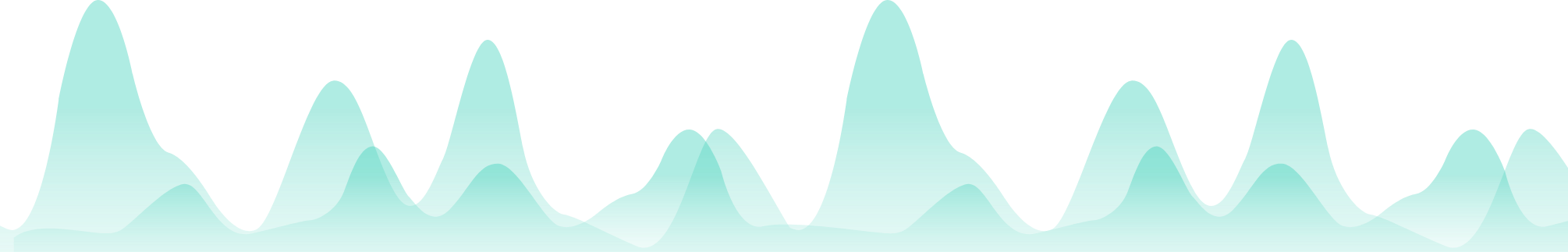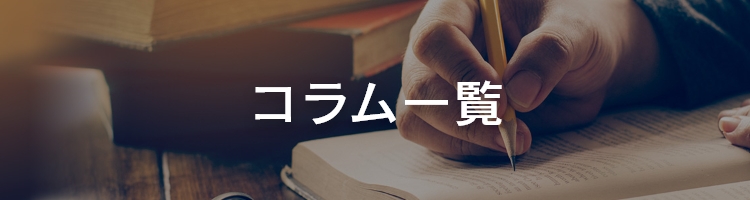
HACCPの危害分析とは?基本知識と対策・システム化について解説

HACCPは、食品の製造過程で発生しうる危害を事前に特定し、コントロールするための国際的な衛生管理システムです。食品の安全性を確保する上で不可欠なシステムの中核をなすのが「危害分析」です。 本記事では、HACCPにおける危害分析の基本的な考え方から、具体的な実施方法、さらには見落としがちなポイントまで詳しく解説します。 HACCPの導入・運用を検討されている方はもちろん、すでに導入済みでより深い理解を求める方もぜひお役立てください。
HACCPにおける危害分析の基本知識
HACCPにおける危害分析は、食品の安全を確保するための出発点であり、最も重要なプロセスの一つです。
この分析を正確かつ網羅的に行うことで、食品事故のリスクを低減し、消費者に安全な製品を届けることが可能になります。
ここでは、危害分析の基本的な定義と食品安全管理における役割、分析を行うべきタイミングについて解説します。
HACCPにおける危害分析の定義と重要性
HACCPにおける危害分析とは、食品の製造から最終消費に至るまでの全工程で、食品の安全性を脅かす可能性のある「危害要因」を特定し、発生する確率や健康への重篤度を評価するプロセスです。危害分析は、HACCPシステムの最も重要な基盤となります。
危害分析は、単にリスクを洗い出すだけでなく、リスク管理の「重要管理点(CCP)」を特定するために不可欠です。この分析が不十分だと、適切な管理ができません。
例えば、加熱工程での微生物の死滅が不十分な場合、食中毒菌が残存する「生物的危害」が発生します。また、アレルギー物質が意図せず混入してしまう「化学的危害」や、金属片が混入する「物理的危害」も危害要因です。これらを事前に特定し、リスクを評価することが危害分析の目的です。
危害分析が食品安全管理に果たす役割・メリット
危害分析は食品安全管理をより確実なものにし、企業に多大なメリットをもたらします。
具体的には以下のようなメリットがあります。
- 食品事故の予防
- 効率的な衛生管理
- 企業の信頼性の向上
危害分析は、潜在的なリスクを可視化して具体的な対策をすることで、未然に事故を防ぐことが可能です。結果的にコスト削減やブランドイメージの保護に繋がります。
実際にHACCPを導入し、危害分析を徹底したことで、製品回収のリスクが減少した食品製造業者があります。また、衛生管理のポイントが明確になったことで、従業員の作業効率が向上し、品質管理にかかる時間も短縮されたという事例も少なくありません。消費者からの信頼も向上し、新たなビジネスチャンスに繋がるケースもあります。
危害分析を行うタイミング
危害分析は一度行えば終わりというものではなく、定期的な見直しや、特定の状況下での再評価が必要です。特に、新製品の開発時や製造工程の変更時、新たな危害要因が判明した際には、速やかに実施することが求められます。
食品を取り巻く環境や技術は常に変化しており、一度設定した危害分析が永続的に有効とは限らないため、適切なタイミングでの見直しが不可欠です。
定期的な見直しと、変化に応じた迅速な対応を心がけることで、常に最適なHACCPシステムを維持し、消費者に安全な食品を提供し続けましょう。
危害分析のやり方

HACCPにおける危害分析を効果的に行うためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、危害要因を正確に特定し、そのリスクを評価するための具体的なステップと、見落としを防ぐための重要なポイントを解説します。
製品の特性を深く理解し、製造工程全体を詳細に分析することで、網羅的かつ実用的な危害分析を行いましょう。
危害分析|基本の5ステップ
HACCPの危害分析は、以下の5つの基本ステップを踏むことで、漏れなく効果的に実施できます。ステップを一つずつ丁寧に進めることが、確実に食品安全管理を行う上で大切です。
- 危害要因の特定(ハザードリストアップ):潜在的危害要因をリストアップ
- 発生確率と重篤度の評価:特定した危害要因を評価
- 管理手段の検討:各危害要因に対する管理手段を検討
- CCP(重要管理点)の決定::危害管理に不可欠なポイントをCCPとして決定
- ハザード分析ワークシートの作成:分析結果を、危害分析表にまとめる
上記のステップは相互に関連しており、一つでもおろそかにするとHACCPシステム全体の信頼性が損なわれます。各ステップで疑問が生じた場合は、専門機関やコンサルタントに相談してみてください。
危害要因の見落としを防ぐ!「製品説明書」の作成
危害要因の見落としを防ぐためには、自社が製造する「製品説明書」を詳細に作成することが重要です。製品に関するあらゆる情報を網羅することで、潜在的なリスクを正確に特定する助けとなります。
製品説明書には、以下のような情報を記載します。
- 製品名
- 原材料:添加物を含む全ての原材料
- 配合:各原材料の配合割合
- 製造方法:調理工程、加熱・冷却方法、包装方法など
- 製品の物理化学的特性:pH値、水分活性(Aw)、塩分濃度など
- 流通・保存方法:冷蔵、冷凍、常温など、推奨される保管温度と期間
- 喫食対象者:特に注意が必要な消費者層
- 喫食方法:加熱調理が必要か、そのまま喫食可能か
製品説明書を徹底的に作成することは、危害要因の特定だけでなく、HACCPプラン全体を構築する上での基盤となります。
製品説明書を作成する際は、製造現場の担当者だけでなく、開発部門や品質保証部門とも連携し、多角的な視点から情報を集めましょう。
製品工程一覧図の作成
製品工程一覧図の作成は、危害分析を行う上で不可欠なステップです。製造プロセスの全体像を視覚的に把握することで、各工程に潜む危害要因を効率的かつ網羅的に洗い出すことが可能になります。
例えば、お弁当の製造工程であれば、以下のような工程が考えられます。
- 原材料の受入(肉、野菜、米、調味料など)
- 原材料の保管(冷蔵、冷凍、常温)
- 下処理(野菜の洗浄、肉のカットなど)
- 調理(加熱、炒め、揚げなど)
- 冷却
- 盛付け
- 包装
- 金属探知
- 製品の保管(冷蔵)
- 出荷 このように工程を洗い出し、各工程で発生しうる危害要因
製品工程一覧図は、危害分析チーム全員が共通認識を持つための重要なツールです。実際に現場を歩き、写真などを活用しながら作成することで、より正確で実用的な図が完成します。見直しや更新も容易に行えるよう、わかりやすくシンプルな図を心がけましょう。
HACCP運用における危害分析を行う際の注意点
HACCP運用における危害分析は形式的な作業ではなく、以下の注意点を踏まえることで、より実効性の高いものになります。特に、「現状を正確に把握する」「専門知識を総動員する」「継続的な見直しを行う」ことがポイントです。
HACCPの危害分析は常に進化するリスクに対応できるよう、継続的な改善が必要です。
以下の注意点を意識することで、より実践的で効果的なものになります。
- 現状を正確に把握する:理想論ではなく、実際の現場を踏まえて分析する
- 専門知識を総動員する:専門知識を持つ人材をチームに入れる
- 文書化と記録の徹底:HACCPプランの根拠が明確になる
- 継続的な見直し:HACCPはPDCAサイクルを回すことで、より強固なものになる
上記の注意点を意識するだけのHACCPではなく、真に食品安全を守るためのHACCPを構築し、企業の信頼性を高めていきましょう。
温度管理における危害分析の重要性とシステム化
食品の安全性を脅かす危害要因の中には、温度管理が直接的に影響するものや、リスクを大きく左右するものが数多く存在します。
中でも、生物の増殖や品質劣化は温度に大きく依存するため、正確な温度管理は危害分析において重要です。
ここでは、温度管理が必要な具体的な危害要因と、従来の管理方法が抱える課題、課題を解決するシステム化の重要性について掘り下げていきます。
温度管理が必要な危害要因の特定
温度管理は「生物的危害」と「物理的危害(一部化学的危害)」の双方において、発生リスクを大きく左右するため、危害分析における管理点を正確に特定することが大切です。
温度は微生物の活動に直接関わるだけでなく、食品の物理的・化学的変化にも影響を与えるため、管理が多岐にわたる危害の予防に直結するものです。
- 微生物の増殖:最も一般的な危害要因。冷蔵・冷凍保存品の温度逸脱による食中毒菌や腐敗菌の増殖。加熱不足による微生物の残存もこれに含まれる
- 毒素の産生:特定の微生物は、増殖過程で耐熱性の毒素を産生することがあり、加熱しても毒素が残るため非常に危険
- 品質劣化:直接的な健康被害には繋がらなくとも、クレームや製品回収の原因となる可能性がある
- 特定の化学的変化:品質劣化や異臭の原因となることもある
危害要因を正確に特定し、各工程での温度管理の重要性を認識することが、効果的なHACCP危害分析の第一歩です。自社の製品と工程において、どの温度帯で、どのような危害要因が発生しうるのかを徹底的に分析してみてください。
従来の温度管理の課題と限界
従来の多くの食品工場や飲食店で行われている手動による温度管理は、HACCPの厳格な要件を満たす上で多くの課題と限界を抱えています。
手動での管理は、人の手による作業である以上、避けられないエラーや効率の悪さが存在し、HACCPが求める「継続的な監視と記録」を完璧に行うことは困難です。
- ヒューマンエラー:従業員による測定忘れ、記録ミス、誤った数値の記入、チェック漏れなど
- 記録の手間と保管:手書きでの記録は、時間と労力がかかる。また、大量の記録用紙の管理や、過去データの検索にも手間がかかり、必要な情報を迅速に参照できない
- リアルタイム性の欠如:問題発生時の初動が遅れ、食品事故のリスクが高まる
- 監査対応の負担:監査時には、膨大な量の記録を提示し、説明する必要がある。改ざんのリスクもあり、信頼性の確保が難しい場合がある
上記の課題を放置することは、HACCP運用の形骸化や食品事故のリスクを高めることに繋がります。HACCPの義務化を機に、より信頼性が高く、効率的な温度管理方法への移行を真剣に検討することで、企業の持続的な成長を目指しましょう。
まとめ
HACCPにおける危害分析は、食品安全管理の根幹をなす重要なプロセスです。適切な危害要因の特定と管理を行うことで、食品事故のリスクを最小限に抑え、安全な食品を消費者に提供できます。
特に温度管理は、微生物の増殖抑制や品質維持において重要な要素であり、正確な管理が危害分析の成否を分けます。
しかし、従来の手動による温度管理では、多くの課題がありました。これらの課題を解決し、より高度で効率的な温度管理を実現するのが、自動温度管理システム「ACALA」です。
ACALAを導入することで、温度データの自動記録、リアルタイム監視、異常発生時の即時通知が可能となり、HACCPにおける温度管理の精度と効率が飛躍的に向上します。
ぜひこの機会に、ACALAによるHACCP対応の強化をご検討ください。