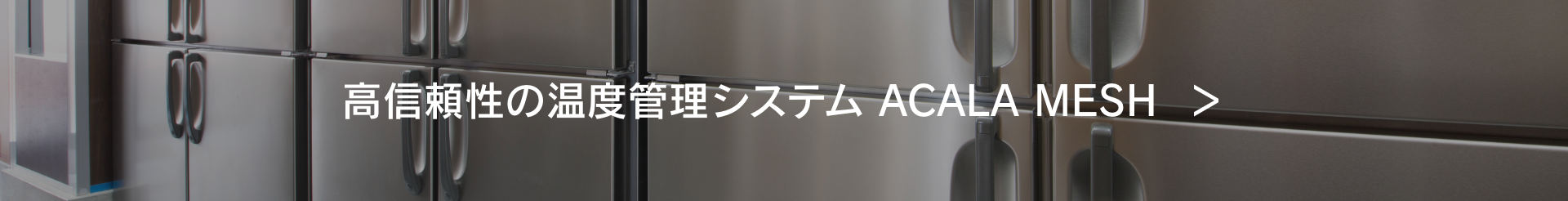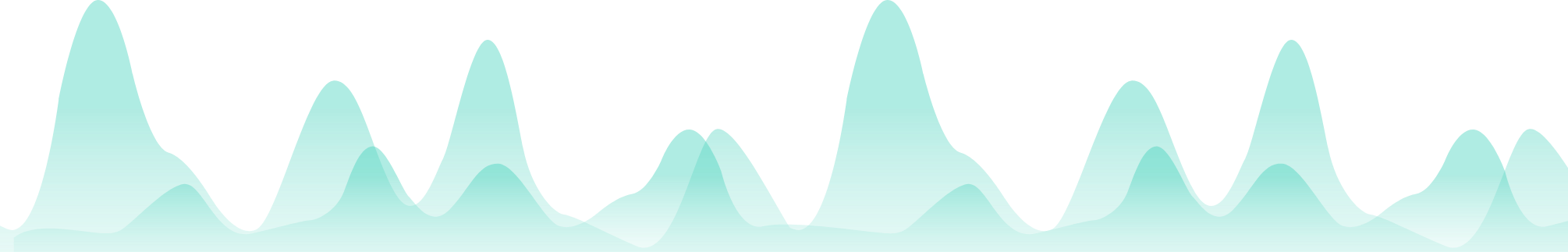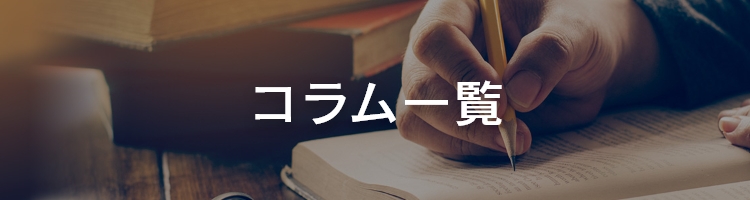
2025年日本の温度は記録更新|食品工場や製造業における実態と対策
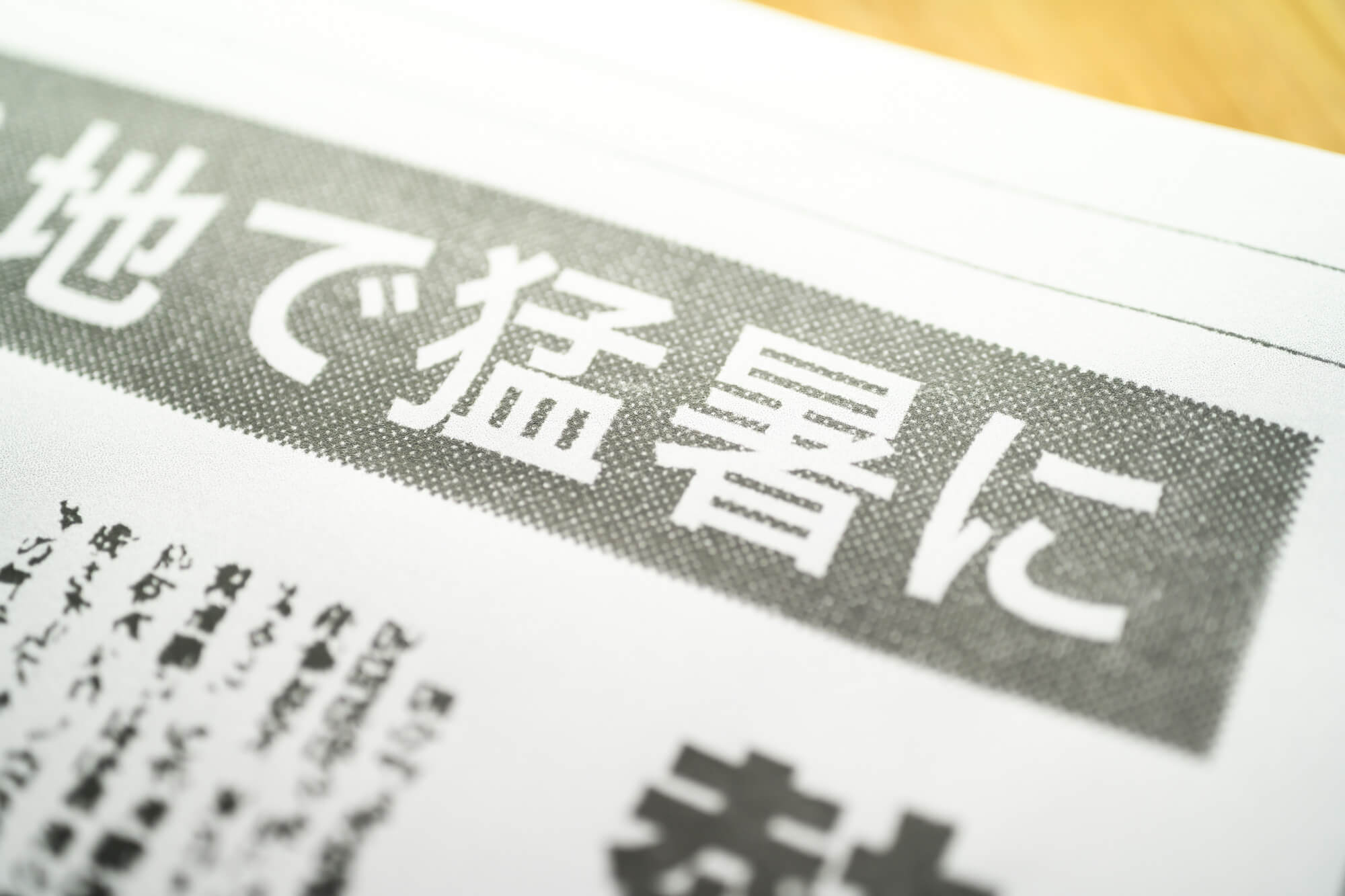
近年、日本の夏は異常なほどの猛暑を記録し、2025年もその記録を更新しました。この気候変動がもたらす事業への影響に懸念を抱いている企業も少なくないでしょう。 この記事では、日本の記録的な高温トレンドが工場や食品製造業に与える具体的なリスクを深掘りし、品質管理の課題、企業として今すぐできる地球温暖化対策まで詳しく解説します。 激化する気候変動の時代において、ビジネスを守り成長させるためにも、ぜひご一読ください。
【日本の温度記録】2025年の記録的な暑さ
日本列島の記録的な暑さ、未曾有の高温は、日常生活だけでなく、品質管理が求められる食品工場や製造業において、深刻な影響を及ぼし始めています。
ここでは、日本が直面する高温の実態をデータに基づいて解説し、気候変動が引き起こすリスクの高い地域や業界について掘り下げていきます。
日本が直面する記録的な高温の実態
気象庁のデータによれば、日本の年平均気温は長期的に上昇傾向にあり、特に近年はその上昇ペースが加速しているといいます。
統計開始以降、過去に例を見ない日本の平均気温の上昇は、もはや一時的な現象ではありません。気候変動による恒常的なものと認識されており、自然変動と地球温暖化が複合的に影響し合っていると考えられています。
自然変動とは、数年〜数十年周期で繰り返される大気の循環や海洋の温度変化など、自然現象による気温の変動を指します。一方、地球温暖化は、人間の活動によって排出される温室効果ガスが地球全体を温めている現象です。
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書でも、地球温暖化が異常気象の頻度と強度を増していることが示されており、日本もその例外ではありません。
日本の最高気温ランキングから見るリスクの高い地域と業界
| 順位 | 都道府県 | 地点 | 観測値(℃) | 起日 |
| 1 | 群馬県 | 伊勢崎 | 41.8 | 2025年8月5日 |
| 2 | 静岡県 | 静岡 | 41.4 | 2025年8月6日 |
| 3 | 埼玉県 | 鳩山 | 41.4 | 2025年8月5日 |
| 4 | 群馬県 | 桐生 | 41.2 | 2025年8月5日 |
| 5 | 兵庫県 | 柏原 | 41.2 | 2025年7月30日 |
| 6 | 静岡県 | 浜松 | 41.1 | 2020年8月17日 |
| 7 | 埼玉県 | 熊谷 | 41.1 | 2018年7月23日 |
| 8 | 栃木県 | 佐野 | 41.0 | 2025年8月5日 |
| 9 | 岐阜県 | 金山 | 41.0 | 2024年7月29日 |
| 10 | 高知県 | 江川崎 | 41.0 | 2018年8月8日 |
これらの歴代記録は、一部の地域だけの問題ではありません。
過去の最高気温記録を見ると、日本各地で高温が観測されています。内陸部に位置する地域では特に高温になりやすく、ヒートアイランド現象も相まって、都市部でさらに気温が上昇する傾向があります。
【日本の温度記録】食品工場・製造業を襲うリスクと品質管理の危機
記録的な猛暑は、食品工場や製造業の品質管理体制に大きなひずみをもたらします。特に食品衛生法で厳しく定められた基準の遵守は、これまで以上に困難を極めるでしょう。
ここでは、猛暑が食品衛生に与える問題点から、温度管理の不備が引き起こす不良品や廃棄品の増加が、企業にどのようなコストと信頼損失をもたらすのかについて解説します。
食品衛生法遵守の難しさ!猛暑が引き起こす具体的な問題
食品工場における温度管理は、食品衛生法に基づきHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられています。しかし、記録的な猛暑は、厳格な基準の遵守をより困難にしているのが実情です。
問題1:食材の鮮度保持と品質劣化の加速
冷蔵・冷凍設備の負荷増大により、庫内温度が上昇しやすくなります。特に、乳製品、肉、魚介類、生野菜などは温度変化に敏感であり、短時間の温度上昇でも品質に影響が出やすいです。
問題2:製造工程における温度管理基準の逸脱リスク
外気温が高くなると、製造工程上で設定された温度を維持することが難しくなり、意図しない温度逸脱が発生しやすくなります。機械設備自体の熱放出や、冷却水の温度上昇も、工程温度の制御を妨げる要因です。
問題3:食中毒菌の増殖・衛生管理におけるリスク
猛暑により工場内の室温や食材の温度が上昇すると、菌が急速に増殖するリスクが高まります。また、高温環境下での作業は、従業員の集中力低下や疲労を招き、衛生管理の手順ミスや交差汚染のリスクが増加しやすいです。
高温環境下での不良品・廃棄品が増加!企業が被るコストと信頼損失
温度管理の不備は、不良品や廃棄品の増加に繋がります。
適切な温度で保管・製造されなかった食品には、変色、異臭、食感の変化などが生じます。変質した製品は市場に出荷できず、全て不良品として廃棄せざるを得ません。
不良品の増加は、原材料費、製造コスト、廃棄費用という負担から、企業の収益は圧迫され、経営に大きな影響を与えます。 特に、大量生産を行う工場では、わずかな温度管理のミスが大量の製品ロスに繋がるのです。
また、不良品が市場に出てしまった場合、消費者からのクレームは避けられません。異物混入と誤解されたり、品質が悪いと判断されたりすることで、企業の信頼は大きく揺らぎます。
企業にとって、経済的な損失だけでなく、ブランドイメージの低下という深刻な問題を引き起こすことにもなるでしょう。
【日本の温度記録】地球温暖化対策として企業ができること

地球温暖化は単なる環境問題ではなく、企業の経営戦略に直結する重要な課題です。記録的な日本の温度上昇に対応するためには、単なる対症療法ではなく、根本的な対策が求められます。
ここでは、日常的な省エネ意識の徹底や業務プロセスの改善から、環境に優しい製品選択、リサイクル・リユースによる資源活用の重要性まで、企業として実践できる地球温暖化対策をご紹介します。
日常的な省エネ意識の徹底と業務プロセス改善
企業活動におけるエネルギー消費は、温室効果ガス排出の大きな要因です。そのため、省エネ意識の徹底と業務プロセスの改善は、地球温暖化対策の基本となります。
高効率LED照明への切り替えや、人感センサー付き照明の導入は、電力消費の削減が可能です。また、空調設備は、設定温度の見直し(夏は高め、冬は低め)、フィルターの定期清掃、ゾーニングによる部分空調などで効率化を図ります。最新の省エネ型空調設備への更新も、長期的な視点で見ればその効果は大きいでしょう。
また、生産ラインの非稼働時間を減らし、効率的な稼働スケジュールを組むことで、設備の待機電力を削減できます。さらに、生産計画の最適化により、急な増産や減産に伴うエネルギーの無駄をなくし、効率的な生産体制の構築が可能です。「ジャストインタイム」生産方式の導入なども有効だといえます。
省エネに関する従業員研修を実施し、一人ひとりが電力消費や資源利用を意識することも大切です。社内での省エネキャンペーンや、目標達成時のインセンティブ導入も効果的でしょう。
環境にやさしい製品選択とリサイクル・リユースで資源活用
持続可能な社会の実現には、企業が調達から生産、廃棄に至るまで全体で環境負荷を低減する、以下のような取り組みが求められます。
環境負荷の低減
- 環境負荷の低いサプライヤーを選定する「グリーン調達」を推進する
- CO2排出量削減のため、輸送ルートの最適化や環境負荷の低い輸送手段への切り替え
- 再生可能エネルギーへの切り替えの検討や節水対策を行う
持続可能な原材料調達と製品開発の推進
- リサイクル素材、再生可能素材、持続可能な方法で生産された原材料を使用する
- 製品設計段階から、長寿命化、修理可能性、リサイクルしやすさを考慮した「エコデザイン」を採用する
- 環境に配慮した新製品の開発を行う
不良品や廃棄品を減らすことによる資源の有効活用
- 製造工程の改善や品質管理の強化により、不良品の発生率を最小限に抑える
- 発生してしまった廃棄物についても、リサイクルやリユースを徹底し、最終的な埋め立て量を減らす努力をする
ACALA導入で実現する食品衛生・品質管理の自動化と高精度化
厳しい気候下において、食品衛生や品質管理に役立つのが、温度管理システムACALAです。ACALAは、工場内の各所に設置されたセンサーから温度データを常時収集し、リアルタイムで監視します。
例えば、ACALAには以下のような特徴があります。
- 設定された温度範囲を逸脱した場合、即座に担当者へアラートを送信
- 冷蔵庫の故障や不調など異常事態の早期発見と迅速な対応が可能
- 手動での記録や目視確認の負担を軽減し、人為的なミスを排除
- 収集された温度データはクラウド上で一元管理され、過去の履歴も詳細に記録
- 温度変動の傾向や問題点を可視化し、より精密な温度管理計画を立てることが可能
- 特定の時間帯や工程で温度が上がりやすい傾向があれば、冷却強化などの対策も可能
自動化されたシステムACALAはヒューマンエラーをなくし、監査対応時のデータ信頼性を高めるだけでなく、遠隔での監視や設定変更により、管理者側の負担軽減も実現可能です。
不良品・廃棄品の削減!ACALAがもたらすコスト削減と企業価値向上
温度管理システムACALAを導入することで、温度逸脱による製品ロスを最小限に抑えられます。精密な温度管理と早期異常検知により、製品の変質や劣化を未然に防ぐことが可能だからです。不良品として廃棄される製品の量を削減し、原材料費や製造コストの無駄をなくせます。
結果として、生産効率が向上し、収益性の改善に繋がります。さらに、高品質な製品を安定的に供給できるようになるため、消費者からのクレームが減少します。 常に一定の品質を保つことで、顧客からの信頼を獲得し、ブランドイメージも向上するでしょう。
さらに、不良品・廃棄品の削減は、食品ロス問題や資源の有効活用といったSDGs目標の達成にも貢献します。省エネ効果や、サプライチェーン全体の環境負荷低減にも寄与し、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも重要です。
まとめ
日本の温度記録が更新され続ける異常気象の時代において、食品工場や製造業はかつてないほどの品質管理の危機に直面しています。食材の劣化、製造工程での温度逸脱、それに伴う不良品・廃棄品の増加は、企業にとって甚大なコストと信頼損失を招きかねません。
そこで最も直接的かつ効果的な対策となるのが、高精度な温度管理システムの導入です。
温度管理ACALAは、製造コストの削減、顧客からの信頼度向上、さらには企業の持続可能な経営を実現します。安定した品質と生産性を維持するためにも、温度管理システムACALAの導入をご検討ください。