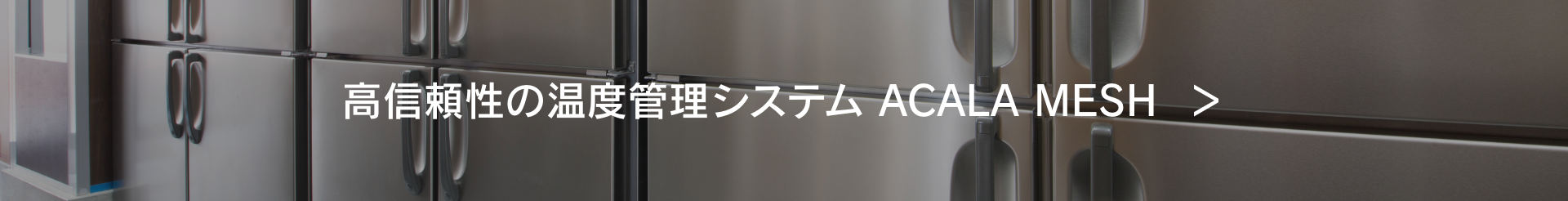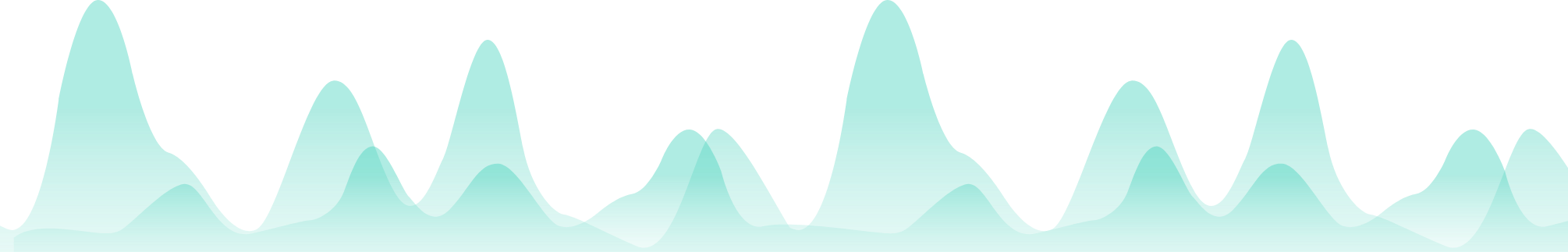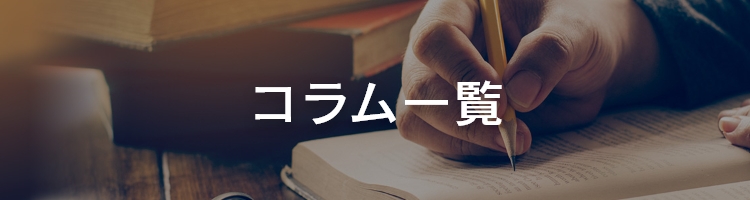
食品衛生の7S活動とは?5Sとの違いや効果的な進め方を解説

食品衛生の一環として7S活動の導入は効果的だとされていますが、従来の5S活動が形骸化している中で、新しい活動を導入するのは負担に感じるかもしれません。 しかし、HACCPの考え方が浸透する現代において、食品衛生の7S活動は食の安全を守り、企業の信頼性を高めるために不可欠な取り組みとなっています。 本記事では、食品衛生における7Sの基本から5Sとの違い、導入によって得られる具体的な効果、失敗しないための活動の進め方を解説します。 7S活動の全体像を理解し、自信を持って現場での導入を推進するためにもぜひご一読ください。
食品衛生における7Sとは?
7S活動の導入を検討する上で大切なことは、目的を理解することです。ここでは、最も基本となる「そもそも7Sとは何か?」という疑問を解消します。
この章では、食品工場で7Sを導入する目的や、多くの方が混同しがちな「5S」との違いなど、7Sの基本を押さえておきましょう。
食品工場で7S活動を行う目的
食品工場で7S活動を行う目的は、食の安全を確保し、企業の持続的な信頼性を構築することです。
2021年6月からHACCP(ハサップ)に基づく衛生管理が完全義務化され、すべての食品等事業者に対して、その土台となる一般衛生管理プログラムの徹底が求められるようになりました。
HACCPの土台を確実に実行するための、具体的かつ体系的な行動指針そのものが7S活動です。
それゆえ、7S活動はHACCPの土台を固め、企業の未来を守るための重要な経営戦略といえます。まずはその目的をチーム全員で共有することから始めてみてください。
5Sと7Sの決定的な違いは「洗浄」と「殺菌」
5Sと7Sの違いは、食品衛生に特化した「洗浄(Senjou)」と「殺菌(Sakkin)」という2つのSが追加されている点です。
従来の5Sは製造業全般の生産性や安全性を高めるための基礎活動ですが、食品を扱う現場では、目に見えない微生物レベルでの管理が不可欠です。
一般的な汚れを取り除く「清掃」だけでは、食中毒の原因となる細菌やウイルスを十分に除去することはできません。
「清掃」で大きな汚れを、「洗浄」で微生物のエサを、「殺菌」で微生物そのものを除去するという段階的なアプローチが、食の安全を守る上で重要です。
食品工場においては、5Sを土台とし、「洗浄」「殺菌」を加えて初めて衛生管理が成り立つと理解しましょう。2Sを加えることが、HACCPの前提条件をより確実に満たすための鍵となります。
食品衛生における7Sの要素

この章では、7Sを構成する「整理・整頓・清掃・清潔・躾・洗浄・殺菌」の7つの要素を紹介します。
それぞれの要素の内容と、活動の具体例を挙げて解説するので、現場で実践する際の明確なイメージを掴みましょう。
1S:整理(Seiri)- 不要なモノを捨てる
1Sの「整理」とは、必要なモノと不要なモノを明確に区別し、不要なモノを捨てる活動です。
不要なモノが職場にあふれていると、作業スペースが狭くなるだけでなく、清掃の妨げになったり、害虫や異物混入の原因になったりします。また、必要なモノをすぐに取り出せないため、作業効率の低下にも繋がるでしょう。
2S:整頓(Seiton)- モノの置き場所と置き方を決める
2Sの「整頓」とは、必要なモノを「誰でも」「すぐに」「安全に」取り出せるように、置き場所と置き方を決めて表示することです。
モノの置き場所が定まっていないと、探すという無駄な時間が発生し、生産性を低下させます。また、無理な姿勢でモノを取ろうとして怪我をするなど、労働安全衛生上のリスクも高まるため、「元に戻すのが楽な仕組み」を作るのがポイントです。
3S:清掃(Seisou)- 常にピカピカの状態にする
3Sの「清掃」とは、単にきれいに見せるだけでなく、ゴミやホコリ、汚れがないピカピカの状態を維持し、同時に設備の点検を行う活動です。
清掃は、異物混入や微生物汚染を防止する基本中の基本です。また、清掃の過程で機械のネジの緩みや油漏れ、部品の摩耗といった「微小な不具合」に気づくなど、トラブルを未然に防ぐ「点検」としての役割も担っています。
4S:清潔(Seiketsu)- 3S(整理・整頓・清掃)を維持・管理する
4Sの「清潔」とは、1S(整理)、2S(整頓)、3S(清掃)を徹底して実行し、きれいな状態を維持・管理する仕組みを作ることです。
清潔は、3S活動の成果を定着させるための重要なステップです。3S活動をしても、維持する仕組みがなければ、後戻りしてしまいます。
4Sは、3Sの状態を「当たり前」のレベルに引き上げ、衛生的な環境を永続的に保つために不可欠です。
5S:躾(Shitsuke)- 決められたルールを習慣化させる
5Sの「躾」とは、職場で決められたルールや基準を、全員が当たり前のように守れる状態、つまり習慣化させることです。
ルールやマニュアルを整備しても、実行する「人」の意識と行動が変わらなければ、全く意味がありません。
躾は、7S活動を企業文化として根付かせるための、最も重要で、かつ最も難しい要素です。ルールの必要性はもちろん、目的や背景を丁寧に伝えるなど、基本的な規律を徹底することが躾の第一歩になります。
6S:洗浄(Senjou)- 目に見える汚れを物理的に除去する
6Sの「洗浄」とは、洗剤などを用いて、目に見える食品カスや油汚れといった、微生物の栄養源となる有機物を洗い流すことです。
清掃が主にホコリやゴミを取り除く「乾いた状態」での作業が中心なのに対し、洗浄は水や洗剤を用いる「濡れた状態」での作業であり、特に微生物が増殖する原因となる「エサ」を徹底的に除去することを目的とします。
7S:殺菌(Sakkin)- 目に見えない細菌を化学的・物理的に死滅させる
7Sの「殺菌」とは、洗浄できれいにした対象物に残存している、目に見えない細菌やウイルスなどの微生物を、化学的または物理的な方法で死滅・不活化させる活動です。
洗浄で微生物のエサを取り除いても、微生物そのものは残存している可能性があります。食中毒を防ぎ、食品の安全性を保証するためには殺菌が欠かせません。
使用する殺菌剤の特性を正しく理解し、マニュアルに定められた用法・用量を遵守することが重要です。
食品衛生7S活動の効果と失敗しない進め方
7S活動を導入することで得られる効果や活動の進め方についても理解しておくことが大切です。
この章では、食品衛生の7S活動で得られる効果と適切な進め方をご紹介します。7S活動の効果を最大限活かすためにも確認しておきましょう。
7S導入で得られる4つの効果
7S活動を導入することにより、単に職場がきれいになるだけでなく、「安全性」「品質」「生産性」「従業員の意識」という4つの側面で効果が得られます。
- 安全性の向上(食品事故リスクの低減)
- 品質の向上(製品の均質化、クレーム減少)
- 生産性の向上(作業の効率化、コスト削減)
- 従業員の意識改革(モラル向上、チームワーク醸成)
7S活動は、安全・品質・コスト・人材育成という、経営の根幹に関わる課題を同時に解決する要素です。7S導入による効果を意識して活動に取り組むことで、より高い成果を目指しましょう。
7S活動の進め方4ステップ
7S活動を成功させるには、「計画→実行→評価→改善」のPDCAサイクルに基づいた4つのステップで進めることが大切です。
- ステップ1:導入計画の策定とチーム編成
- ステップ2:現状把握とエリアごとの目標設定
- ステップ3:7S活動の実行と記録
- ステップ4:効果測定と改善(PDCAサイクル)
場当たり的な活動は目的が曖昧になりやすく、従業員のモチベーション低下や活動の形骸化を招く原因になります。明確な計画と目標に基づき、全社的に取り組む体制を構築し、継続的に活動を進めることがポイントになります。
まとめ
7S活動とは、従来の5Sに食品衛生に特化した「洗浄」と「殺菌」の2Sを加えた活動です。7S活動は食の安全を根本から支え、品質や生産性の向上や従業員の意識改革まで繋がる、重要な経営活動です。
活動を推進するためには、現場の従業員一人ひとりが‘目的を共有し、意識を高めることが大切です。
まずは自社の現状を把握し、小さなステップから7S活動を始めることをおすすめします。小さな一歩が工場の衛生管理レベルを引き上げ、信頼の獲得にも繋がるでしょう。
活動記録や効果測定を効率的に行うには、専門ツールの活用が有効です。活動の見える化は、従業員のモチベーション維持にも繋がり、PDCAサイクルを円滑に回す強力なサポートとなるため、ぜひ導入をご検討ください。