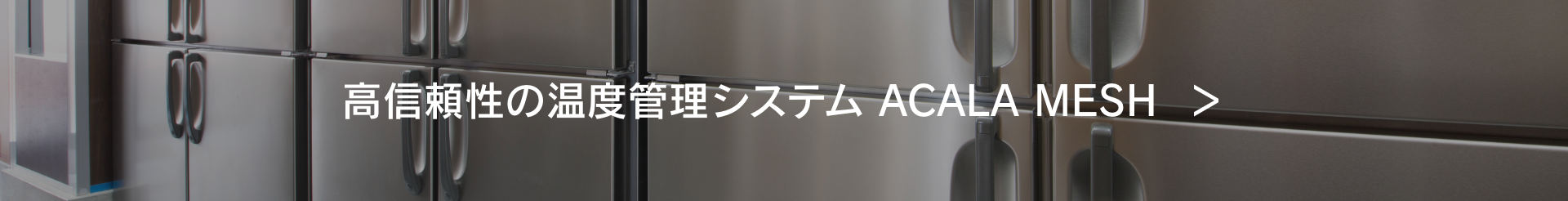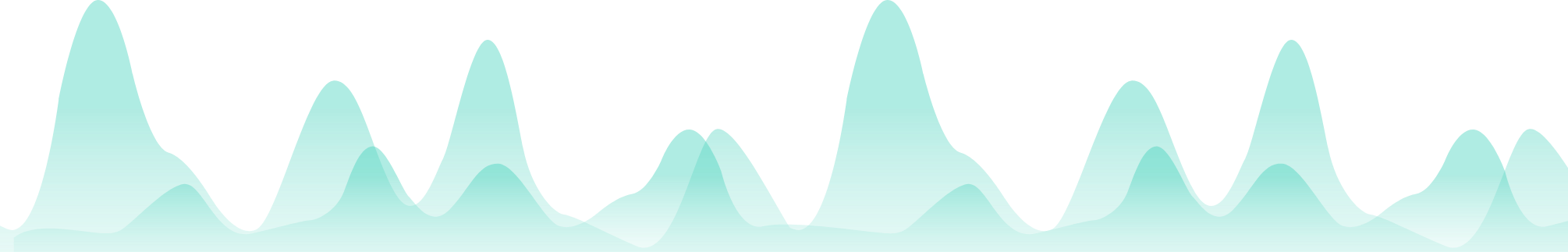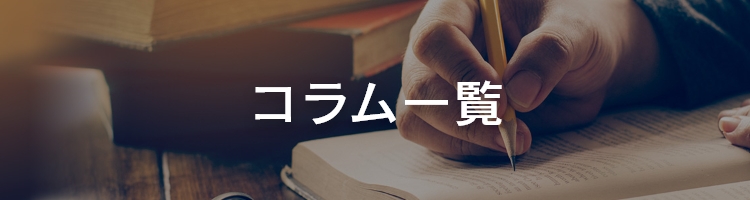
病院のDX化に利用できる補助金は?

病院は早急なDX化が求められている場所ではあるものの、取り組みが順調に進んでいるとは言い切れません。病院でDX化が進まない大きな理由に「高額な導入コスト」が挙げられます。そこで本記事では、病院のDX化を後押しするために活用できる2つの補助金について解説します。
病院のDX化には補助金を利用しよう
病院におけるDX化は、高額な導入コストが大きな障壁となっています。DX化に必要な機器の導入やシステムの更新、患者の個人情報を守るセキュリティ対策、機器を使いこなす人材の確保や育成などには多大な費用が必要で、病院の経営を圧迫するためです。
人手不足による人件費と採用費の増加、病床稼働率の低下などにより経営が厳しくなり、DX化を進める経済的な余裕がない医療機関も少なくありません。しかし、DXを進めると業務が効率化され、将来的にコスト削減につながることが期待できます。DX化により医療品質や利便性が向上して患者の満足度が高まれば、収益の増加も見込めます。
そこで利用したいのが補助金制度です。政府は、DX化を進める病院の負担を軽減するために補助金制度を設けています。高額な導入コストをDX化のハードルに感じている病院は、補助金の活用を検討してみましょう。
次から、病院のDX化に活用できる「医療情報化支援基金」と「IT導入補助金」という2つの制度を紹介します。
医療情報化支援基金
医療情報化支援基金とは、医療分野のICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)化を支援するために令和元年に新設された補助金制度です。
医療情報化支援基金は、高齢者をはじめとしたすべての人が、自身が居住する地域で自分らしい暮らしを続けながら医療サービスを受けられる「地域包括ケアシステム」の一環として導入されました。また、ICT化の推進により効率的かつ高品質な医療を提供することも目的としています。
対象となる事業
医療情報化支援基金の対象となる事業は、主に以下の3つです。
- オンライン資格確認の導入
- 電子カルテシステムの導入
- 電子処方箋管理サービスの導入
オンライン資格確認とは、患者が加入している医療保険を確認する作業をオンラインで行うことを指します。これまでは保険証の現物を受け取り、内容を確認してシステムに手入力していました。
しかしマイナンバーカードを活用すれば、ICチップを読み込んだり記号番号を入力したりするだけで資格確認ができるため、作業の手間と時間が大幅に削減されます。さらに、資格の一元管理や、医療機関のシステムで管理されている患者情報との紐付けも容易になり、患者の利便性や医療品質の向上も期待できます。
電子カルテシステムは、患者の医療情報を従来の紙のカルテではなく、電子データで一元管理するシステムのことです。医療情報化支援基金では、とくに国が指定する標準規格を用いた電子カルテシステムの導入について支援を行います。国が指定する電子カルテシステムを利用すると、全国の医療機関で情報共有が可能になるため、質の高い医療を提供できるようになります。
電子処方箋管理サービスは、処方箋の運用を電子的に管理するシステムです。処方箋の電子管理により、複数の医療機関や薬局で処方・調剤された情報を共有し、重複投薬や併用禁忌などのチェックを容易に行えるようになります。また、紙の処方箋を紛失するリスクがなくなることは患者にとってのメリットといえます。
申請方法
オンライン資格確認の導入では、まず必要な機器を選定して購入します。次に「医療機関等向け総合ポータルサイト」にてユーザー登録を行います。オンライン資格確認の利用を申請し、アプリをダウンロードして機器の設定や運用の準備を行いましょう。
その後、機器を購入した領収書、領収書内訳書、助成金交付申請書をポータルサイト上にアップロード、または郵送することで申請が完了します。
電子カルテシステムと電子処方箋管理サービスについても、基本的に同様の流れで申請します。電子カルテシステムや電子処方箋サービスを運用できる環境を整備して、システムベンダなどに費用を支払い、領収書を受け取りましょう。その領収書と領収書内訳書などの必要書類をアップロードまたは郵送することで、補助金を申請できます。
それぞれ申請条件や申請に必要な書類が異なるため、よく確認してから申し込んでください。
IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際に利用できる補助金制度です。企業の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX化に向けたITツールの導入を支援するために設立されました。
病院も、常勤の従業員が300名以下であれば利用できます。IT導入補助金にはインボイス枠やセキュリティ対策推進枠など、目的別に5つの枠が用意されていますが、電子カルテシステムの導入などは基本的に「通常枠」で申請します。
対象となる事業
IT導入補助金の対象となるのは、IT導入支援事業者があらかじめ事務局に登録したツールに限られます。医療機関の申請対象となるITツールの主なものには、電子カルテ、医療デジタル画像管理、レセコンがあります。電子カルテは先述の通り、患者の医療情報を電子データで一元管理するシステムのことです。
医療デジタル画像管理とは、レントゲンや内視鏡などで撮影した画像をデータで保存するシステムを指します。PACS(Picture Archiving and Communication System)と呼ばれる医療用画像管理システムの利用により、これまで写真やフィルムなどに印刷して保管していた画像を、ネットワーク上で保存できるようになります。PACSを導入すると画像の管理や共有が容易になるうえに、保管スペースが削減されることもメリットです。
レセコンはレセプトコンピューターの略であり、レセプト(診療報酬明細書)を作成するシステムを指します。いまや多くの病院で導入されているレセコンですが、電子カルテと連携することでより効率的にレセプトを発行できるようになります。すでにレセコンを導入している病院も、IT導入補助金を利用して電子カルテとの連携を進めるとよいでしょう。
申請方法
IT導入補助金を申請する流れは、次のとおりです。
- 公募要領の確認
- 「gBizIDプライム」のアカウント取得と「SECURITY ACTION」宣言の実施
- 「みらデジ経営チェック」の実施
- IT導入支援事業者の選定とITツールの選択
- 申請書の作成と提出
- 交付決定通知の受け取り
- ITツールの発注・契約・支払い
- 事業実績の報告
- 補助金交付
- 事業実施効果の報告
これらのステップのなかで、申請書の作成、事業実績の報告、事業実施効果の報告はIT導入支援事業者と共同して行うことになります。また、gBizIDプライムのアカウント取得、SECURITY ACTION宣言の実施、みらデジ経営チェックの実施は、通常枠の申請要件とされています。
申請書や報告書の作成、アカウントIDの発行などには時間がかかるため、早めに準備を進めましょう。
まとめ
病院のDX化には、業務効率化や患者の利便性改善、医療品質の向上などのメリットがあります。しかし導入コストが高額なため、DX化があまり進んでいないのが現状です。
補助金制度を利用すると負担を軽減してITツールやシステムを導入できますが、申請には条件があり、手間と時間もかかります。病院のDX化は低コストなものから導入し、小さく始めるのも方法のひとつです。
医薬品の温度・湿度管理を自動化できるIoTシステム「ACALA MESH」は、病院のDX化のスタートに最適です。機器はレンタルで提供され、サーバやソフト、サービスに対する月額料金を支払うだけで利用できるため、初期費用を抑えられます。コストを抑えて業務効率化を目指すなら、「ACALA MESH」の利用を検討してみてください。