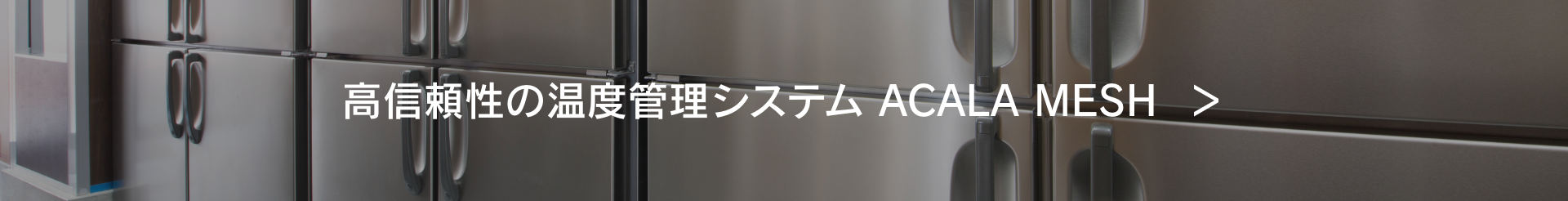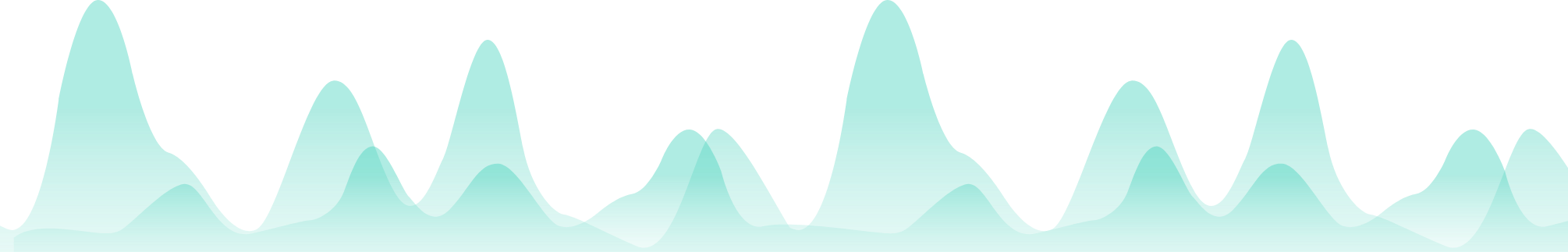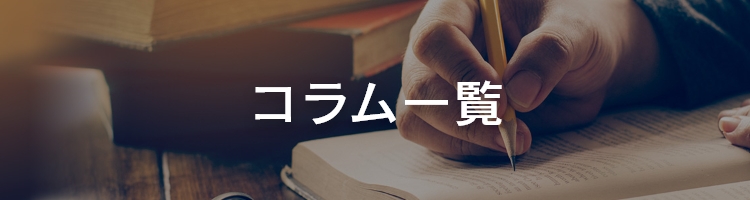
温度管理「常温」とは何度まで?定義や曖昧な管理によるリスクを解説

常温保管の製品の管理では、夏の暑い倉庫や配送中のトラックにおける品質管理に注意が必要です。 実は、多くの方が当たり前に使っている「常温」という言葉の曖昧さが、気づかぬうちに品質劣化や食中毒、法令違反といった重大なビジネスリスクを生む温床になっています。 本記事では、「常温」の正しい知識から、曖昧な管理が引き起こすリスク、課題を解決する方法まで、日々の管理に悩む品質管理担当者様が知っておくべき情報を解説します。 「常温」の温度管理に悩まずに、取引先からも消費者からも信頼される品質体制を構築するためにもぜひご一読ください。
温度管理における「常温」とは?JIS規格や法律での定義
本章では、「常温」の定義について、JIS規格や食品衛生法、物流現場で使われる「3温度帯」など、それぞれの基準を解説します。
「常温」が指す温度は置かれる状況によって異なります。なぜ管理を難しくしているのか、その原因が見えてくるはずです。
JIS規格(日本産業規格)における「常温」の定義
JIS規格(日本産業規格)では、「常温」は5℃から35℃の範囲と定義されています。
これは、工業製品の性能試験や化学分析などを行う際の環境条件を統一し、時間や場所による測定結果にばらつきが出ないようにするためです。
例えば、製品の耐久試験を行う際、夏と冬で室温が大きく異なると正確なデータが取れません。そのため、JIS Z 8703「試験場所の標準状態」では、常温を5~35℃、さらに「室温」を1~30℃と定め、安定した試験環境の基準を設けています。
JIS規格における「常温」は、あくまで試験環境の基準であり、必ずしも食品保存の基準を指すわけではないことを理解しておきましょう。
食品衛生法における「常温」の定義
食品衛生法や、その下部法令である食品表示基準には、「常温」を具体的に「何度」と定義する規定はありません。
食品の種類や包装形態、殺菌方法によって適切な保存温度が異なるため、法律で一律に温度を定めることが実質的に不可能なためです。
例えば、チョコレートとスナック菓子はどちらも「常温保存」と表示されますが、チョコレートは28℃を超えると溶け始める一方、スナック菓子は湿気を避ければ比較的高い温度でも品質を保てます。
このため、具体的な温度管理は製造者の責任において設定され、その判断に委ねられているのが現状です。
食品における「常温」には法的な数値基準がなく、製造者が保証する品質を保てる範囲で管理する必要がある、ということになります。
何度で管理すべき?「常温を超えない温度」という考え方
法的な定義がない中、実務上の「常温」は「意図的に加熱も冷却もせず、外気温を超えない温度」で管理するのが一つの目安となります。
「常温を超えない温度」は、特別な空調設備を使わずに、自然な状態で保管することを前提とした考え方です。
直射日光が当たる場所に製品を置くと、外気温が30℃でも製品自体の温度は40℃以上に上昇することがありますが、この場合「外気温を超えた」状態であり、常温管理の範囲を逸脱しています。そのため、風通しの良い、直射日光の当たらない場所で保管するのが基本です。
近年の猛暑に対応するためには、製品パッケージに記載されたメーカー推奨の保存方法を守り、「常温を超えない温度」での管理が重要になります。
食品の3温度帯
物流や食品業界では、一般的には商品を「常温」「冷蔵」「冷凍」の3つの温度帯に分類して管理します。この3温度帯は、多種多様な食品の品質を最適に保ちながら、効率的に輸送・保管するための業界の仕組みです。
具体的には、「冷凍」は-18℃以下、「冷蔵」は10℃以下、それ以外の加工食品や飲料、米などが「常温」に分類されます。
食品管理の基本となる「3温度帯」を理解し、その中で「常温」がどのような位置づけにあるかを知ることが、適切な温度管理を行う上で大切です。
【要注意】曖昧な「常温」の温度管理が引き起こす3つのリスク

近年、35℃・40℃といった猛暑が引き起こす品質劣化や食中毒は重大なリスクを引き起こす要因のひとつです。また、2021年から完全義務化されたHACCPへの適切な対応による法令順守や、温度管理による高い品質管理も求められています。
本章では、ずさんな温度管理は品質管理において、3つのリスクについて解説します。
1. 35℃・40℃の高温による品質劣化と食中毒
35℃を超えるような高温環境は、「常温保存」と表示された食品であっても品質劣化や食中毒のリスクを高めます。
多くの食品に含まれる油分は高温で酸化しやすく、また食中毒を引き起こす細菌の多くは20℃~40℃の温度帯で最も活発に増殖するためです。
例えば、ポテトチップスのような揚げ菓子は、高温の倉庫に長期間保管すると油が酸化して不快な臭いや味の原因になります。また、密封されたレトルト食品であっても、万が一包装にピンホールがあれば、高温下で細菌が急激に増殖し、食中毒事故につながる恐れがあるため、注意が必要です。
たとえ常温保存品であっても、夏場の35℃・40℃といった高温環境は品質と安全を脅かす重大なリスク要因となります。
2. HACCP義務化と管理不備による法令違反
HACCPに沿った衛生管理において、温度管理の記録の不備は法令違反とみなされる可能性があります。
2021年6月から完全義務化されたHACCPでは、科学的根拠に基づいた衛生管理が求められており、温度は食中毒菌の増殖を抑えるための「重要管理点(CCP)」に定められることが多いです。
例えば、保健所の査察が入った際に、倉庫の温度記録が毎日つけられていなかったり、基準温度を逸脱した際の対応記録がなかったりすると、HACCPの基準を満たしていないとして指導の対象となります。
悪質なケースでは、営業停止などの行政処分につながる可能性もゼロではありません。適切な温度管理とその記録は、企業のコンプライアンスを守る上で避けては通れない必須事項となっています。
3. ずさんな管理体制が招く取引先・消費者からの信頼の失墜
曖昧な温度管理体制は、取引先や最終消費者からの信頼を大きく損なう原因となります。
近年、食の安全に対する社会の目はますます厳しくなっており、特に大手小売業者や食品メーカーは高いレベルの品質管理を求める傾向にあるためです。
例えば、新規取引の際の工場監査で、手書きの温度記録に記録漏れなどがあった場合「品質管理意識が低い」と判断され、取引が見送られる可能性があります。また、万が一品質問題が発生すれば、SNSなどを通じて瞬く間に情報が拡散されれば、ブランドイメージは大きく傷つくでしょう。
ずさんな温度管理は、ビジネスチャンスの喪失やブランド価値の低下に直結するため、企業にとって見過ごせない経営リスクです。
従来の「常温」温度管理方法と限界・解決策
多くの現場で今も行われている、1日2回の目視チェックと手書きによる温度記録ですが、その裏には記録漏れなどのヒューマンエラーや、人手不足・管理コストの増大といった深刻な問題が潜んでいます。
本章では、従来のアナログ管理が抱える問題点を明らかにし、それらを根本から解決するDX(デジタルトランスフォーメーション)ソリューションをご紹介します。
1日2回の目視と手書きによる記録の限界
1日2回の目視確認と手書きでの記録という従来の方法では、正確で継続的な温度管理は困難です。
記録漏れや記入ミスといったヒューマンエラーが発生しやすく、夜間や休日など人のいない時間帯の温度変化を全く把握できないという致命的な欠点があります。
例えば、担当者が忙しさのあまり朝の検温を忘れ、記憶で数値を記入する、といったことは容易に起こり得ます。また、夜間に空調設備が故障して倉庫の温度が急上昇しても、翌朝出勤するまで誰もその事実に気づけず、手遅れになるケースもあるでしょう。
人の手と目に頼ったアナログな管理方法では、HACCPが求める継続的な監視の要求を満たすことができず、重大なリスクを見逃す可能性が高いです。
温度計の精度と設置場所の問題
従来の方法における温度計の精度や設置場所も、適切な温度管理を妨げる要因となります。
安価な温度計には誤差があることや、倉庫内の場所によって温度が均一ではない「温度ムラ」があるため、一点だけの計測では倉庫全体の温度環境を正しく維持しているとは言えません。
倉庫の出入り口付近や天井付近は、床の中央部とは温度が大きく異なることがあります。壁に設置した一つの温度計だけを見て「問題なし」と判断していても、実は倉庫の奥で保管している製品は高温にさらされている、という危険性があります。
温度計の定期的な校正や複数箇所への設置といった対策が必要ですが、アナログ管理では手間とコストがかかるため、限界があります。
人手不足と管理コストの増大
手書きによる温度管理は、人手不足が課題である現場において、見えない管理コストを増大させる要因となっています。
温度のチェックや記録用紙への記入、ファイリング、監査時の書類準備といった一連の作業は、従業員の貴重な時間を奪い、本来注力すべき業務を圧迫するためです。
人手に頼る温度管理は、人件費という直接的なコストだけでなく、機会損失という間接的なコストも生み出しています。
常温の温度管理をDX化|「ACALA」が解決
これまで述べてきた従来型管理の限界は、当社が提供する温度管理システム「ACALA」の導入により解決できます。
「ACALA」は、IoTセンサーとクラウド技術を活用し、温度管理の自動化、可視化、効率化を実現するDXソリューションです。
具体的には、以下の3つの特徴があります。
- 24時間365日、どこからでも自動で温度を記録・監視
- アラート通知により温度異常をすばやく検知
- HACCPガイドラインに準拠した管理体制の構築が容易
「ACALA」は人手不足による問題の解消、管理コストの削減、信頼性の高い品質管理体制の構築を同時に実現し、曖昧な常温管理の課題を解決する最適な選択肢です。
まとめ
本記事では、「常温」という言葉の定義が曖昧である事実と、それにより引き起こされる深刻なリスクについて解説してきました。
- 「常温」に統一された定義はなく、JIS規格や業界慣習に依存する
- 夏場の高温は、常温保存品の品質を劣化させ、HACCP違反にも繋がりかねない
- 手書きでの温度記録は、ヒューマンエラーやコスト増大の限界にきている
これらの課題は、担当者の努力だけでカバーできる範囲を超えています。食の安全と企業の信頼を守り、現場の負担を軽減するためには、管理体制そのもののアップデートが不可欠です。
そのために有効な手段となるのが当社の温度管理システム「ACALA」です。まずは公式サイトで詳細を確認し、導入をご検討ください。