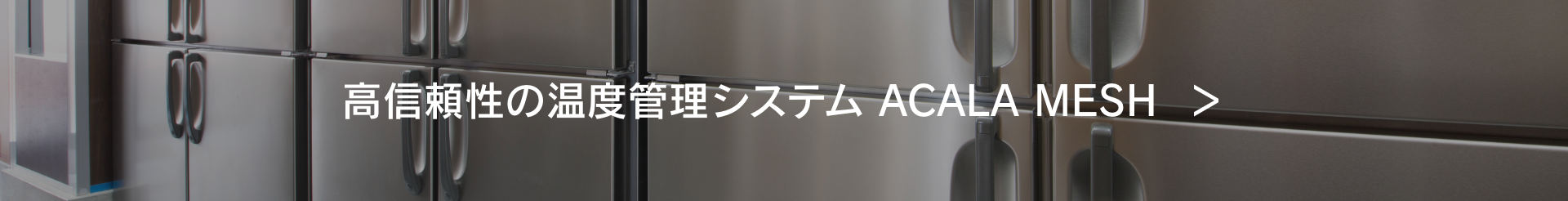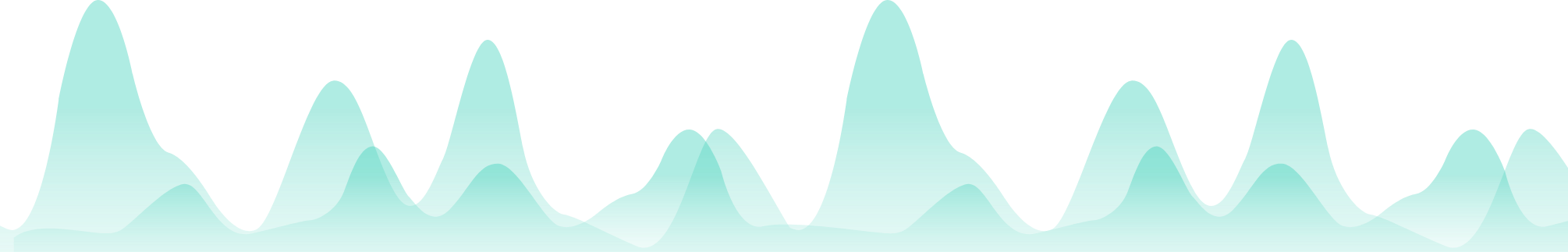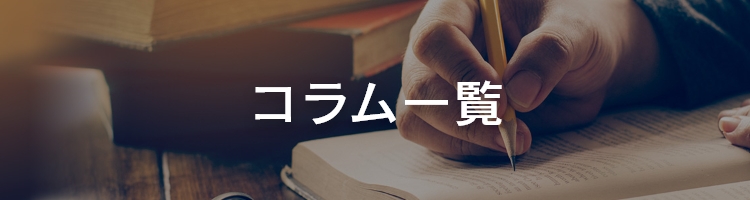
食品衛生法のポジティブリストとは?対象物質や事業者に求められる対応を解説

食品衛生法に基づくポジティブリストという言葉を耳にしたことはありますか?ポジティブリストとは、食品衛生法の中でも、食品の安全性を守る上で必須のルールです。 本記事では、食品衛生法に基づくポジティブリストについて、目的やネガティブリストとの違い、対象物質や事業者に求められる対応について解説します。食品に関わる方が知っておくべき基礎知識ですので、ぜひご一読ください。
食品衛生法におけるポジティブリスト
食品衛生法におけるポジティブリストについて、基本的な概念から導入の経緯、類似制度であるネガティブリストとの違いがあります。
ポジティブリストを実施する際は、食の安全確保においてどのように貢献しているのか、その仕組みを理解することが大切です。
また、ネガティブリストとの違いを把握し、安全管理への取り組みを強化しましょう。
ポジティブリストとは?
ポジティブリストとは、食品用基部や容器包装において、安全性を評価し物質や使用可能な量などの条件をまとめた一覧表を指してものです。使用を認められたもの以外は、原則として使用が禁止されています。
ポジティブリストの施行日と経過措置
ポジティブリストは、食品用器具や容器包装においては、安全が評価された物質の使用のみ認めることとして、令和2年6月1日から施工されました。
施工後も令和7年5月31日までは、経過措置において、次のような規定があります。使用が認められる物質は施工日以前に販売されたもの、もしくは輸入され、営業上使用されている器具または容器包装の物質で、使用実績の範囲内に限られます。
以下は、本経過措置の対象にはなりません。
- 未使用の合成樹脂区分の基ポリマーに添加剤を加える場合
- 添加剤を従来の使用上限を超える量を使用する場合
- 製造記録や輸入実績等によりこれまで使用されていた範囲内を説明できない場合
ネガティブリストとの違い
食品の安全性を確保するための規制の考え方には、大きく分けて「ポジティブリスト制度」と「ネガティブリスト制度」の2種類があります。両者は規制のアプローチが根本的に異なります。
| 制度 | 考え方 | メリット | デメリット |
| ポジティブリスト | 原則禁止、例外的に許可 | 安全性が高い、規制対象が明確 | 新規物質導入に時間、リスト管理の手間 |
| ネガティブリスト | 原則自由、例外的に禁止 | 新規物質の導入が容易、規制対象が限定的 | 未知のリスクに対応できない可能性 |
・ポジティブリスト制度:「原則禁止、例外的に許可」
安全性が評価され、使用(または食品への残留)が許可された物質だけをリスト化し、そのリストに載っていない物質の使用(残留)は原則として禁止する方式です。
・ネガティブリスト制度:「原則自由、例外的に禁止」
有害性が確認されたものや、使用(含有)を禁止すべき物質だけをリスト化し、そのリストに載っていない物質の使用(含有)は原則として自由とする方式です。
ネガティブリストでは、安全が確保されていなくても使用できますが、ポジティブリストではより厳しくなっており、原則安全が確保されたものだけしか使用できません。
しかし、ポジティブリストの導入により、安全性が確保されていない危険性があるものを排除でき、食の安全レベルを高められます。
ポジティブリストの対象物質

ポジティブリストの対象となる物質は、基本的に物質ごとの含有量もしくは添加量で管理されており、必要に応じて溶出量や制限が規定されています。
消費者が安心して食品を購入できるよう、ポジティブリストにおける対象物質をチェックしましょう。
ここでは、ポジティブリストにおいて対象となる物質として、残留農薬等における対象物質食品用器具および容器包装における対象物質に分けて、それぞれについて解説します。
ポジティブリストで対象となる物質
品衛生法のポジティブリスト制度は、食品の安全性を確保するために、特定の化学物質等を対象としています。具体的には、主に以下の2つのカテゴリーの物質が対象となります。
- 「残留農薬等に関するポジティブリスト制度」
- 農薬:残留基準の規制がない農薬等を含む食品の場合、一律基準0.01Ppmが適用されます。基準値を超える残留農薬が認められる食品は原則禁止されます。
- 飼料添加物・動物用医薬品:これらの物質が食品に残留している場合、許可されるのはポジティブリストに含まれる物質のみです。ただし、人の健康を損なわない物質に関して規制の対象外となる場合もあります。
②「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」
ポジティブリストの目的と事業者に求められる対応
消費者の健康を守るためには、食の安全性確保における確実な規制が必須となります。ポジティブリストは、食品中の有害物質を厳しく管理し、安全性を確保する目的で導入されました。
ここでは、ポジティブリストの目的と事業者に求められる具体的な対応について確認していきます。
ポジティブリストの目的
これまでのネガティブリストでは使用可能な物質も多く、食品の安全性の確保に限界がありました。そのため、安全で使用が認められたもののみをリスト化したポジティブリストを導入し、より安全に管理することを可能にしました。
ポジティブリストの目的は大きく以下の2つです。
- 食品の安全性の確保:より厳格な基準で管理することが可能
- 国際的な食品安全基準との整合:国際基準に対応するために導入に至る
実際、多くの欧米諸国ではすでに制度が導入されており、国際基準との整合性を取ることで、海外への輸出促進にも繋がっています。残留農薬の基準は国際基準であるコーデックス基準をもとに設定されたものです。
事業者に求められる対応
事業者に求められる具体的な対応は、以下の3つです。
① 製造工程における管理体制の徹底
食品の製造・加工工程において、ポジティブリストに該当する物質が意図せず混入したり、基準値を超えて残留したりしないよう、衛生管理や品質管理の基準であるGMP(Good Manufacturing Practice)を遵守することが重要です。原材料の受け入れから製品の出荷に至るまで、各工程での汚染リスクを低減するための手順を確立し、実践する必要があります。
② 事業者間の情報伝達について
原材料供給者から製造・加工業者、最終製品の販売者まで、サプライチェーンに関わる全ての事業者間で、使用される化学物質に関する正確な情報を円滑に伝達する体制構築が求められます。サプライヤーに対して、使用履歴や安全性に関する情報の積極的な開示を求め、契約等でその遵守を明確にすることが有効です。特に輸入食品については、輸出国と日本の規制双方への適合を確認する必要があります。
③ 製造事業者の届出
器具や容器包装製造を取り扱う事業者は、食品用器具や容器包装を製造する事業者が、管轄の保健所などに営業届出を行わなくてはなりません。関連事業者の把握と監視を行う体制を確立し、食品の安全性を確保することを目的としています。
届出の対象事業者や届出の詳しい説明は、各地域の保健所や保健センターのホームページなどで確認しましょう。
まとめ
食品衛生法におけるポジティブリストは、安全性が評価され基準値が設定されたもの以外は、原則として使用を認めないという考え方に基づいています。制度の遵守は食品事業者において必須事項です。危険リスクから消費者を守り、食品の安全性を高いレベルで確保できます。
事業者、消費者共に、使用する原材料や製品が基準に適合しているかを常に確認し、最新の情報を把握することが求められます。食品の安全性に対する意識を高め、正しい知識を持ちましょう。