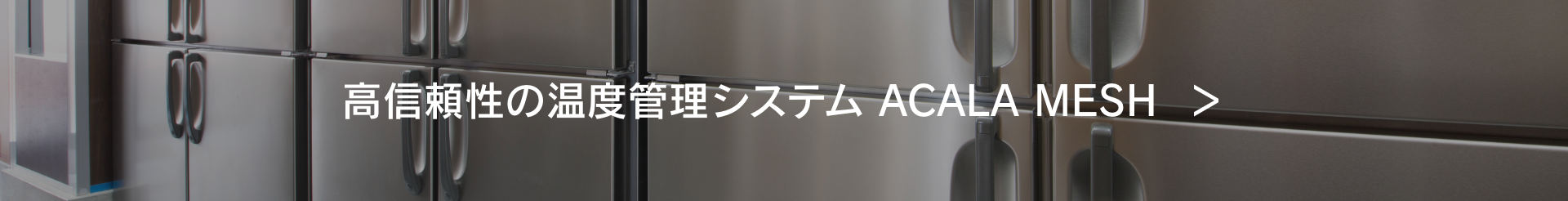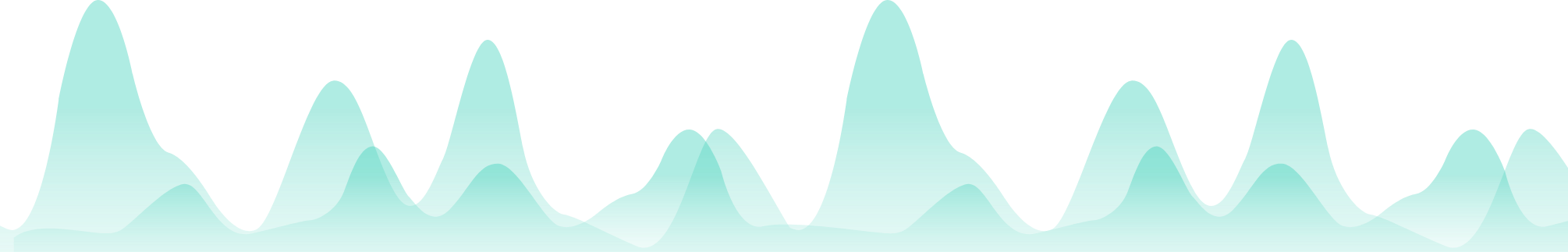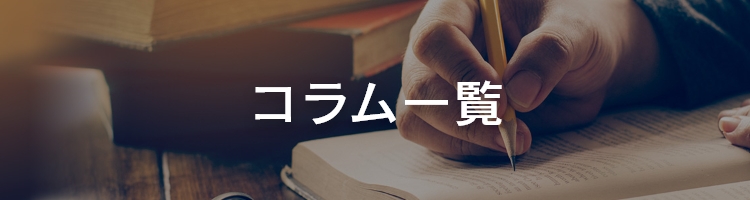
食品衛生における三原則!原因と今すぐできる実践的な対策を紹介

食品の衛生管理は、お客様の信頼に直結する重要な課題です。しかし、長年の経験則だけに頼った指導では、従業員全員の意識を統一するのは難しいでしょう。 特に新しく入った従業員に「食品衛生の三原則」を教える際は、「なぜそうするのか」まで説明することが大切です。 本記事では、厚生労働省が示す「食品衛生の三原則」について、三原則の基本から食中毒の主な原因菌、日々の業務に落とし込むための実践的な対策まで詳しく解説します。 「食の安心・安全」を守るためにもぜひご一読ください。
食品衛生の三原則とは?
食品衛生の三原則とは、食中毒を引き起こす細菌やウイルスへの対策を体系的にまとめたものです。日々の衛生管理の根幹をなす考え方であり、食に関わる上で理解しておく必要があります。
この章では、以下の食品衛生の三原則の内容と具体策をご紹介します。
原則1「つけない」:菌を持ち込まない・広げないための具体策
食品衛生の第一歩は、食中毒の原因となる菌を「つけない」ことです。菌による汚染は、人・器具・食材などによるものが考えられます。
菌を「つけない」ためには、汚染防止別に次の対策が有効です。
- 人からの汚染防止:調理前の手洗いの徹底、清潔な作業着の着用、使い捨て手袋の適切な使用、従業員の健康管理。
- 器具からの汚染防止(二次汚染防止):肉用・魚用・野菜用でまな板や包丁を使い分ける、使用後の調理器具は速やかに洗浄・消毒する。
- 食材からの汚染防止:生の肉や魚のドリップが他の食材にかからないように保管場所を分ける、納品された食材は段ボール箱から出して保管する。
厨房内に菌を持ち込まず、食材や器具に付着させない、広げない対策を徹底する必要があります。
原則2「増やさない」:菌の増殖をストップさせる温度管理の徹底
食中毒菌を「増やさない」ためには、徹底した温度管理が重要です。
環境別の温度管理の具体策は以下の通りです。
- 冷蔵管理:冷蔵庫内は10℃以下、チルド室は0℃前後を維持する。
- 冷凍管理:冷凍庫内は-15℃以下に保つ。
- 調理後の管理:温かい料理は65℃以上で保温、提供しない場合は粗熱を取り速やかに10℃以下に冷却(目安は2時間以内)。
- 仕入れ・解凍:仕入れた食材は速やかに冷蔵・冷凍庫へ。冷凍食材の解凍は、常温解凍を避け、冷蔵庫内や流水で行う。
厨房内の冷蔵庫・冷凍庫それぞれに温度計を設置し、始業時と終業時に温度をチェック・記録し、「見える化」して管理を徹底しましょう。
原則3「やっつける」:菌を確実に死滅させる加熱・殺菌のポイント
食品衛生の3つ目の原則は、菌を「やっつける」ことです。加熱や殺菌で菌を死滅させましょう。
食材の加熱と殺菌のポイントは以下の通りです。
- 加熱:厚みのある食材は中心温度計で内部の温度を測定する。スープやカレーなどの液体は、時々かき混ぜながら十分に煮沸する。
- 殺菌(非加熱):生で食べる野菜や果物は、流水で十分に洗浄する。調理器具は、洗浄後に熱湯をかけたり、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)の希釈液に浸けたりして殺菌する。
厚生労働省は、食中毒予防の加熱条件として「中心部の温度が75℃で1分間以上(二枚貝などに起因するノロウイルス対策では85℃~90℃で90秒間以上)」を推奨しています。
細菌やウイルスの多くは加熱することで死滅するため、食品の中心部まで十分に火を通すことが重要です。
殺菌に使用する次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)は、製品の指示に従い、適切な濃度に希釈して使用してください。
食中毒の主な原因となる細菌
食中毒予防を行うためには、まず原因菌やウイルスの特徴を知ることが大切です。
O157やカンピロバクター、サルモネラ菌など、特に警戒すべき細菌はどこに潜み、どうすれば対策できるのでしょうか。
この章では、食中毒を引き起こす主な原因菌とウイルスの特徴をご紹介します。
腸管出血性大腸菌(O157など):生肉の取り扱いに注意
腸管出血性大腸菌(O157など)は、牛などの家畜の腸内にいることが多く、生肉や加熱不十分な肉料理が主な原因となります。少ない菌量でも発症し、重篤な症状を引き起こすため、厳重な対策が必要です。
カンピロバクター:鶏肉の加熱不足が最大の原因
カンピロバクター食中毒は、発生件数が最も多い食中毒の一つであり、その原因の多くは鶏肉の加熱不足です。鶏刺しや鶏のタタキといった生食メニューはもちろん、加熱したつもりの料理でも感染リスクがあります。
サルモネラ菌:卵や食肉からの感染リスク
サルモネラ菌による食中毒は、卵や食肉(特に鶏肉や豚肉)、うなぎなどが主な原因となります。サルモネラ菌は乾燥に比較的強いという特徴があり、調理器具や手指を介した二次汚染にも注意が必要です。
セレウス菌:チャーハンやパスタなどの作り置きに注意
セレウス菌は、土壌や水など自然界に広く存在する細菌で、チャーハンやピラフ、パスタといった米・麺類の作り置きが原因になりやすい食中毒です。熱に強い「芽胞(がほう)」を形成するため、加熱しても死滅しない場合があります。
黄色ブドウ球菌:調理スタッフの手指が感染源
黄色ブドウ球菌による食中毒は、調理する人の手指が感染源となるケースがほとんどです。特に、手指に切り傷や化膿創がある人が、素手でおにぎりやサンドイッチを作ることが原因となります。
ボツリヌス菌:自家製の瓶詰や真空パックは要注意
ボツリヌス菌は、土壌や海、川などに広く存在する細菌で、酸素のない状態で増殖し、強力な神経毒を作り出すのが特徴です。致死率が高い危険な食中毒であり、特に自家製の瓶詰や真空パック食品、いずし(魚の発酵食品)などが原因となります。
【冬場も注意】ノロウイルスなどウイルス性食中毒との違い
食中毒は細菌だけが原因ではありません。冬場に流行するのが、ノロウイルスに代表される「ウイルス性食中毒」です。ウイルスは食品中で増殖しないなど細菌とは異なる性質を持つため、違いを理解した上で対策を講じる必要があります。
食品衛生の三原則を徹底する!今すぐできる実践策

食品衛生の三原則を徹底するためには、その知識を日々の業務に落とし込み、「仕組み」を作ることが大切です。
知識として知っているだけでは、日々の忙しい業務の中で意識は薄れてしまいます。
この章では、現場で今日からすぐに実践できる具体的な対策をご紹介します。
1. スタッフの健康と身だしなみチェック
衛生管理の徹底は、従業員一人ひとりの健康状態と身だしなみのチェックから始まります。
身だしなみは、以下の点をチェックしましょう。
- 爪は短く切り、マニキュアはつけない
- アクセサリーは外す
- 清潔なユニフォームと帽子を正しく着用し、髪の毛が外に出ないようにする
2. 正しい手洗い手順とタイミングの徹底
正しい手洗いは、最も効果的な食中毒予防策です。正しい手順と、手洗いが必要な「タイミング」を全従業員が共有し、徹底することが求められます。
厚生労働省が推奨する正しい手洗い手順は以下の通りです。
- 流水で手を濡らし、石鹸をつけ
- 手のひらをよくこする
- 手の甲をのばすようにこする
- 指先・爪の間を念入りにこする
- 指の間を洗う
- 親指と手のひらをねじり洗いする
- 手首も忘れずに洗う
最後に流水で十分にすすぎ、清潔なペーパータオルで拭き乾かすまでがワンセットです。
手洗いが必要なタイミングは、以下の通りです。
- 厨房に入る前、トイレの後
- 調理を開始する前
- 生の肉・魚・卵を触った後
- 盛り付けの前
- 清掃作業の後
食中毒の原因となる細菌やウイルスの多くは、石鹸を使った洗浄によって洗い流せます。また、二次汚染を防ぐ上で、作業の区切りごとに行う手洗いは特に重要です。
3. 使い捨て手袋の過信は禁物!正しい使い方
使い捨て手袋は、手指の傷をカバーしたり、素手で触れることによる汚染を防いだりする上で有効です。しかし、使用方法を誤ると、かえって汚染を広げる「汚い手」になってしまうため、注意する必要があります。
手袋交換のタイミングは以下の通りです。
- 作業内容が変わる時
- 手袋が破損した時
- トイレに行く、鼻をかむなどの行為の後
- 一定時間以上、同じ作業を続けた時
正しい手袋の使い方は以下の通りです。
- 手袋を着用する前後は、必ず手洗いを行う。
- 手袋を着用したまま、髪や顔、スマートフォンなどを触らない。
- 使用した手袋は再利用せず、その都度廃棄する。
「手袋は汚染されるもの」という前提に立ち、適切に使用することが大切です。「生肉用」「盛り付け用」など、作業別に手袋の色を変えるのも、交換意識を高めるのに効果的です。
4. 調理器具の洗浄・消毒マニュアル
清潔に見える調理器具でも、目に見えない細菌が付着している可能性があります。
二次汚染を防ぐためには、「洗浄」と「消毒(殺菌)」をセットにした正しい手順をマニュアル化し、誰もが同じレベルで実践できる体制を整えることが大切です。
調理器具別洗浄・消毒方法は以下の通りです。
■まな板・包丁
- 使用後すぐにスポンジと洗剤で洗浄する。
- 熱湯(80℃以上)をまんべんなくかける
- 次亜塩素酸ナトリウム(200ppm)に5分以上浸漬<
■ふきん・タオル
- 洗剤でよくもみ洗いする
- 煮沸消毒(沸騰したお湯で5分以上)
- 次亜塩素酸ナトリウム(200ppm)に5分以上浸漬</td>
■スポンジ
- 使用後によく洗い、水気を切る
- 煮沸消毒(沸騰したお湯で5分以上)
【応用編】食中毒予防「4原則」|ウイルス対策を強化する新常識
近年、食品衛生の三原則に「持ち込まない」を加えた「食中毒予防の4原則」という考え方が、ウイルス対策の観点から重要視されています。
ノロウイルスのように、感染者の便や嘔吐物を介して外部から厨房内に「持ち込まれる」ケースが多発しているためです。
ウイルスは食品中で増殖しないため、「増やさない」対策が通用しません。そのため、ウイルスの侵入そのものを防ぐ「持ち込まない」という入口対策が重要です。
まとめ
本記事では、食中毒予防の核となる「食品衛生の三原則」の具体策や、食中毒の原因となる菌、今すぐできる実践策について解説しました。
衛生管理は、食中毒を未然に防ぐことはもちろん、企業の信頼と未来を守るための重要な経営課題です。
紹介した実践策を参考に、まずは「手洗い手順の周知の徹底」や「始業前の健康チェック」など、できることから始めてみてください。タイムマシーン株式会社の「ACLCA」のような温度の自動記録システムを活用すれば、三原則の内の2つ、「ふやさない」「やっつける」を効率的に実践することが可能です。こまめな温度確認と記録は人手では不可能に近いです。ぜひ、食品衛生のレベル向上と現場の労務軽減を目的に導入をご検討ください。日々の小さな積み重ねにより、「食の安心・安全」を確固たるものにしましょう。