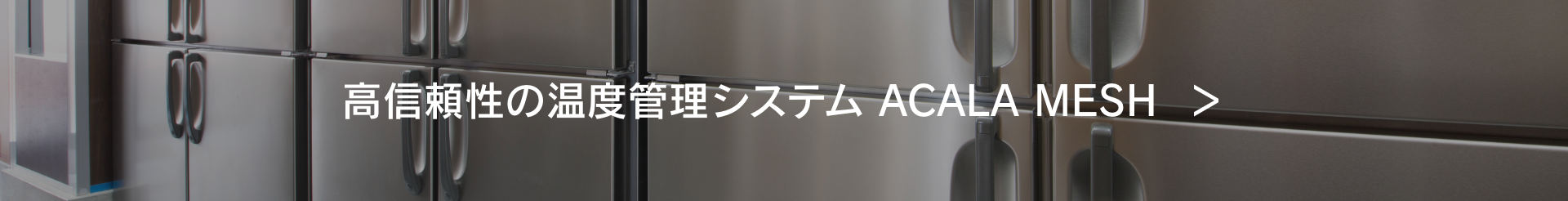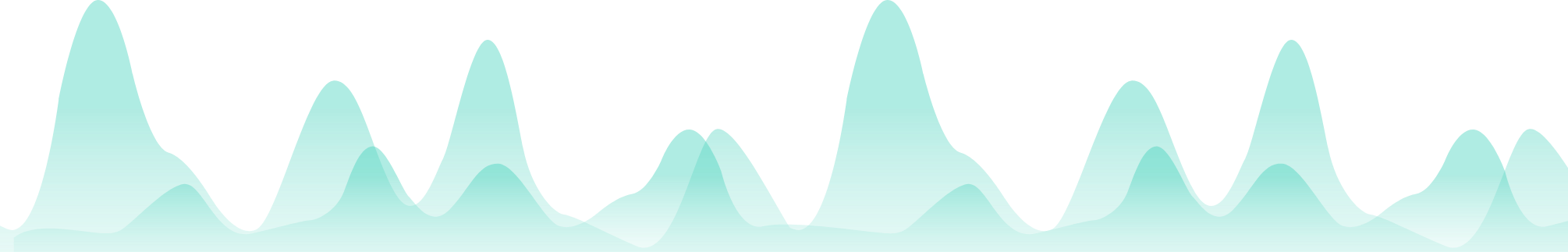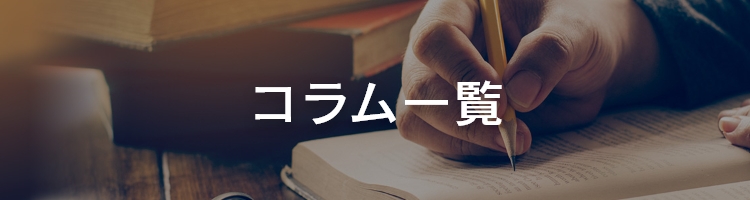
食品製造において熱中症対策は必須!効果的な対策を紹介

食品製造現場における熱中症対策は、従業員の安全確保はもちろん、製品の品質維持や生産性向上にも直結する課題です。 しかし、従来の対策を漫然と続けているだけでは、熱中症リスクを根本から断ち切ることは難しく、最悪の場合、重大な労働災害や生産活動の停止といった事態を招きかねません。 本記事では、食品製造における熱中症の実態や課題、効果的な対策、社内ルールと教育体制について解説します。適切な対策を講じるためにも、ご一読ください。
食品製造における熱中症の深刻さとは
食品製造の現場は、夏季は高温多湿な環境になりやすく、熱中症のリスクが高まります。
食品製造での熱中症は、単に従業員の体調不良を引き起こすだけではありません。生産効率の低下やヒューマンエラーによる製品品質への影響、企業の安全配慮義務に関わる重大な問題に繋がる可能性があります。
この章では、食品製造現場における熱中症の実態と対策の重要性、見落とされがちな課題点について掘り下げていきます。
食品製造の現場での熱中症の実態
食品製造の現場では、熱中症による労働災害が後を絶たず、実態は深刻です。
食品製造業は、厚生労働省「令和6年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況」においても、熱中症による死傷者数が多い業種の一つとして挙げられています。
背景には、加熱調理工程での熱源、ボイル殺菌などによる高温多湿な環境、衛生管理上必須となる帽子、マスク、長袖長ズボンの作業服着用といった、熱がこもりやすい特有の作業条件があります。
例えば、ある食品工場では、夏場のピーク時に複数の従業員がめまいや吐き気を訴え、作業を一時中断せざるを得ない状況が発生しました。
また、別の事例では、集中力の低下から製品への異物混入リスクが高まったという報告もあります。これらの「ヒヤリハット」事例は、重大な事故や品質問題につながる一歩手前の事態です。
食品製造の現場における熱中症は、決して他人事ではなく、自社の問題として捉え、実態を正確に把握することが、効果的な対策を講じるための第一歩となります。
食品製造の現場で熱中症対策の重要性
食品製造の現場における熱中症対策は、単に従業員の健康を守る側面だけでなく、企業の持続的な成長と発展にとっても重要な取り組みです。
労働安全衛生法において、事業者は労働者の安全と健康を確保する義務を負っており、熱中症対策もその一環です。対策を怠り熱中症による労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性があります。
熱中症対策はリスク管理の観点だけでなく、生産性向上や品質確保、企業価値向上にも繋がる重要な経営課題と認識し、積極に取り組むことが重要です。
食品製造における熱中症の課題
食品製造の現場では、一般的な工場とは異なる特有の課題が存在することにより、効果的な熱中症対策の導入を難しくしています。
HACCPなどの衛生管理基準を遵守するためには、工場内の清浄度を保つ必要があり、外部からの汚染防止のため窓を開放しにくく、特定の空調設備の使用にも制約が生じてしまうのが実情です。
また、加熱殺菌工程やオーブン、フライヤーなどの熱源が工場内に多数存在し、局所的に高温環境が形成されやすいのも懸念点だといえます。
食品製造業特有の課題を深く理解し、衛生管理との両立を前提とした上で、工場環境や作業内容に対する最適な熱中症対策の検討や選択が不可欠です。
間違った水分補給に注意
熱中症予防の基本として「こまめな水分補給」が推奨されます。しかし、方法を誤ると体調不良や、熱中症のリスクを高める状態を招く場合があるため注意が必要です。
大量の汗をかくと、水分だけでなく体内の塩分(ナトリウムなど)も失われます。この状態で水だけを大量に摂取すると、血液中の塩分濃度が薄まり、「低ナトリウム血症(水中毒)」を引き起こすことがあるのです。
そのため、従業員に対して、正しい水分や塩分補給の知識(タイミング、量、飲料の種類)を指導し、作業場所の近くに適切な飲料を常備するなど、サポート体制や環境を整えることが大切です。
食品製造における効果的な熱中症対策

食品製造における熱中症のリスクを低減し、従業員が安全かつ快適に作業できる環境を整備するためには、多角的なアプローチによる対策が不可欠です。
前章で述べた熱中症の深刻さを踏まえ、この章では実際に食品製造の現場で実施可能な、具体的かつ効果的な熱中症対策をご紹介します。ぜひ、自社の状況に合わせて取り入れられる対策を実践してみてください。
工場でできる改善
工場全体として作業環境を改善することが、熱中症対策の基本的で効果的なアプローチです。
作業環境そのものが改善されれば、個々の従業員の体調や意識レベルに左右されることなく、工場全体として熱中症のリスクを低減できます。
具体的な改善策として、以下のようなことが挙げられます。
・空調制御システムを導入する:広範囲な作業エリアの環境改善に繋がる。WBGT値を効果的に低減させ、作業者の身体的負担を軽減。
・スポットクーラー、大型扇風機等の送風機を設置する:工場全体の空調だけではカバーしきれない特定の高温作業エリアや、熱がこもりやすい場所に設置するのが効果的。
・ビニールカーテンなどの間仕切りを活用する:工場内のエリアごとの温度管理を効率化し、熱の拡散や冷気の流出を防ぐ。
・吸排気フードを設置する:温湿度上昇を抑制するだけでなく、作業者の呼吸器への影響や視界不良、壁や天井の汚染や結露を防ぐ効果もある。HACCPの観点からも推奨される衛生管理対策の一つ。
・涼しい作業着を導入する:高機能な作業着は、衣服内にこもる熱や湿気を効率的に外部へ放出し、汗による不快感や体力の消耗を抑える。
個人でできる対策
工場側の環境改善努力と並行して、個人的な熱中症の予防対策を実施することも、従業員一人ひとりが自身の健康と安全を守るために不可欠です。
個人の体調や暑さへの耐性はそれぞれ異なるため、一律の環境対策だけではカバーしきれない部分を補う必要があります。
例えば、以下のような対策が有効です。
・こまめな水分補給と塩分補給:発汗によって失われる水分と塩分(電解質)を、のどの渇きを感じる前にこまめに補給する。
・ファン付きの作業服や冷却グッズの活用:実際の気温よりも涼しく感じられ、不快感を軽減できる。ネッククーラーなどの冷却グッズは効率的に体温の上昇を抑える効果がある。
食品製造において熱中症を防ぐ社内ルールと教育体制
食品製造における熱中症対策は、設備の導入や個人の心がけだけでなく、企業全体として取り組むべき重要な課題です。
効果的な対策を継続的に実施し、全従業員の安全意識を高めるためには、明確な社内ルールを整備し、適切な教育体制を構築する必要があります。
この章では、食品製造現場における熱中症を未然に防ぎ、万が一の事態にも対応できる体制づくりのための具体的なポイントを解説します。
食品工場内のWBGT値を把握する
食品工場内の暑熱環境を客観的に評価し、熱中症リスクを管理するための基本的な指標として、WBGT(湿球黒球温度:暑さ指数)値を定期的に測定し、把握することが大切です。
WBGT値は、気温だけでなく、湿度、日射・輻射熱といった熱中症リスクに影響を与える全ての要素を総合的に評価した国際的な指標です。
数値を把握することで、作業環境の危険度を客観的に判断し、それに応じて作業時間の調整や休憩の頻度増加などの具体的な対策を講じることが可能になります。
熱中症対策の研修を実施する
全従業員を対象とした熱中症対策に関する研修を、定期的にかつ継続的に実施することが、組織全体の予防意識と対応能力を高める上で大切です。
熱中症は、その初期症状が風邪や疲労と似ているため見過ごされやすく、正しい知識がなければ適切な予防行動や早期発見、迅速な応急処置ができません。
研修を通じて、熱中症について体系的に学ぶことで、従業員一人ひとりが「自分事」として捉え、主体的に対策に取り組むようになります。
休憩場所を確保する
高温環境下での作業負担を軽減し、従業員の体力を回復させるためには、適切に管理された涼しく快適な休憩場所を確保することが大切です。
定期的な休憩は、体内に蓄積された熱を放散させ、深部体温の上昇を抑えるために欠かせません。休憩場所の環境が劣悪であったり、十分な休憩時間が取れていなかったりすると、疲労が回復せず、熱中症のリスクが高まります。
休憩場所は、単に「休む場所」ではなく、「積極的に体をクールダウンさせ、次の作業に備えるための場所」と位置づけるのもポイントです。従業員が気兼ねなく利用でき、心身ともにリフレッシュできるような環境づくりを心がけましょう。
健康管理と日々の体調チェックの習慣づくり
従業員一人ひとりが日常的に健康状態を維持し、睡眠不足や疲労蓄積といった熱中症のリスクを高める要因を避けることが大切です。毎日の作業開始前に体調をチェックする習慣を確立することが、熱中症の未然防止に繋がります。
熱中症は、体調によって発症しやすさが大きく左右されるものです。特に、睡眠不足、疲労、風邪気味、二日酔い、下痢といった状態は、体温調節機能や水分・電解質バランスを低下させ、熱中症のリスクを高めます。
熱中症は組織全体で予防に取り組むべき問題であるという意識を持ち、体調が優れない場合に正直に申告でき、周囲も理解を示してサポートする環境を醸成することが大切です。
熱中症発症時の初期対応マニュアルを整備する
万が一、職場で熱中症の疑いがある従業員が発生した場合に、迅速かつ適切に初期対応(応急処置と医療機関への連携)ができるようマニュアルを整備することが求められます。マニュアルを全従業員に周知徹底することは、重症化を未然に防ぐためにも重要です。
マニュアルは作成するだけでなく、定期的な研修や訓練を通じて、全従業員が内容を深く理解し、いざという時に冷静かつ迅速に行動できるようにしておくことが重要です。
また、実際に熱中症が発生した場合は対応状況を検証し、マニュアルの改善に繋げていくことも忘れてはいけません。
まとめ
食品製造工場特有の高温多湿な環境や衛生管理上の制約は、熱中症リスクを高める大きな要因の一つです。従来の対策だけでは限界がある中、作業環境の見直しの工夫や服装、作業方法の改善、個人の意識向上、WBGT値の把握や研修、マニュアル整備といった社内体制の重要性も押さえておくべきポイントです。
熱中症対策は、働く従業員の健康を守るのはもちろん、生産性の維持や向上にも繋がります。
本記事でご紹介した情報が、貴社の食品製造における熱中症対策の見直しや、より安全で快適な職場環境を実現するための一助となれば幸いです。
既存の対策に限界を感じている企業様は、この機会に「ACALA」導入を含めた具体的な改善策をご検討ください。従業員と製品の安全を守り、熱中症ゼロの工場を目指すためにも、導入をおすすめします。