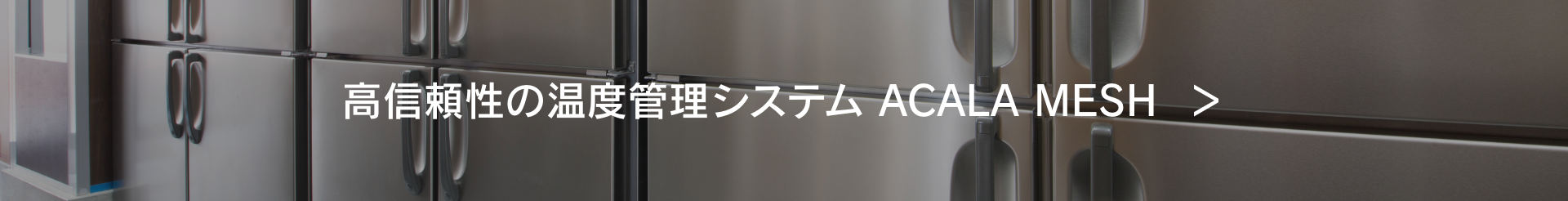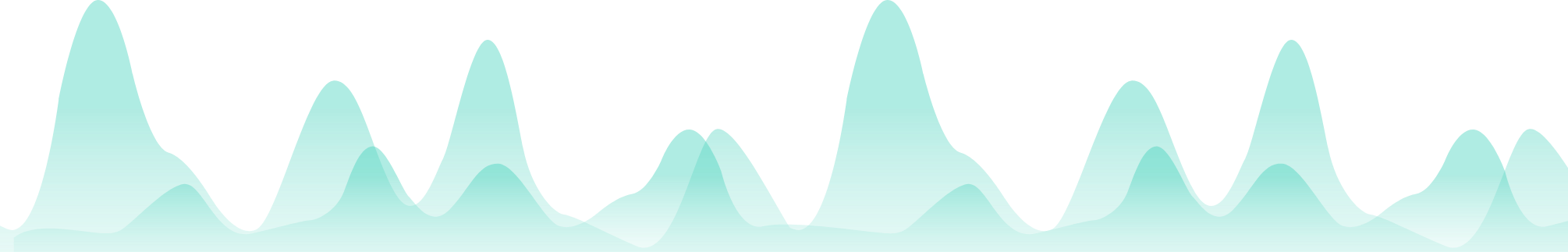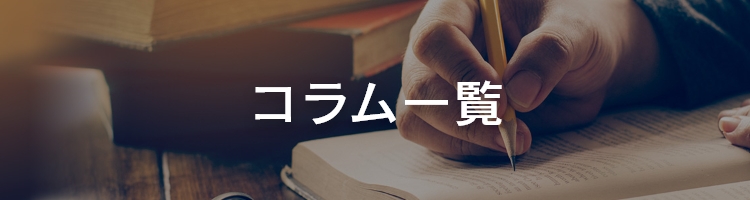
食品衛生の対策ポイント5つのカギと3原則とは?

安全な食を提供するためには、食品衛生に関する正しい知識と日々の対策が不可欠です。 本記事では、食品衛生の基本的な目的から、具体的な予防策として5つのカギや食中毒予防の3原則、近年重要性が増しているHACCPの取り組みまで解説します。 食の安全性を確保するためにも、日々の衛生管理を見直してみましょう。
食品衛生の目的と5つのカギ
食品衛生を実践する上で、具体的でわかりやすい指針として、WHO(世界保健機関)が提唱する「食品をより安全にするための5つのカギ」があります。効果的な衛生管理の基本原則なので、しっかり押さえておきましょう。
食品衛生の概要と目的
食品衛生とは、食品の安全性を確保し、飲食に起因する健康被害を防ぐためのあらゆる手段を指します。主な目的は、食中毒の発生を未然に防ぎ、お客様の健康を守ること、企業の信頼と評判を維持することです。
食品が細菌やウイルス、化学物質などで汚染されると、食中毒を引き起こす可能性があります。食中毒は、お客様に健康被害を与えるだけでなく、営業停止、賠償責任、信用の失墜など、深刻な事態を招きかねません。
だからこそ、食品衛生の徹底は企業において最優先事項です。まずは食品衛生の重要性を再認識し、企業全体で意識を高めることから始めましょう。
食品衛生の5つのカギ
世界保健機関(WHO)が提唱する「5つのカギ」は、食品が危険な微生物に汚染されるリスクを最小限に抑え、万が一汚染された場合でも微生物の増殖を防ぎ、死滅させるための具体的な行動指針を示しています。
・清潔に保つ
手や調理器具、調理場所を常に清潔に保ち、調理前や生肉・生魚を扱った後、トイレの後などには石鹸を使って丁寧に手洗いを行うことが基本です。また、まな板や包丁は食材ごとに使い分けるか、使用の都度、洗浄・消毒することが求められます。
・生の食品と加熱済み食品とを分ける
生の肉、魚、卵などには食中毒菌が付着している可能性があります。これらの食材と、そのまま食べるサラダや加熱済みの料理とが接触しないように、まな板や包丁を使い分けたり、冷蔵庫内で保管場所を分けたりすることが大切です。
・食品を十分に加熱する
ほとんどの食中毒菌は加熱によって死滅します。特に肉料理は中心部まで十分に加熱することが大切です。中心温度が75℃で1分間以上の加熱が目安です。
・食品を安全な温度で保管する
食中毒菌の多くは10℃から60℃の温度帯で活発に増殖します。そのため、調理済みの食品を室温で長時間放置せず、冷蔵庫なら5℃以下、冷凍庫なら-15℃以下で速やかに保管することが大切です。温かい料理を提供する際も、65℃以上で保温するようにしましょう。
・安全な水と原材料を使う
水を使用する場合は定期的な水質検査を行い、安全性を確認する必要があります。また、原材料は信頼できる業者から仕入れ、新鮮で傷みのないものを選び、消費期限や賞味期限を確認することが大切です。
日々の業務の中で、これらのポイントが確実に守られているか、定期的にチェックする習慣を付けましょう。
食品衛生の対策ポイントと食中毒予防3原則

食品衛生の原則を理解したら、次はそれを日々の具体的な行動に落とし込むことが大切です。ここでは、衛生対策のポイントと食中毒予防3原則をご紹介します。
食品衛生の対策ポイント
食品衛生を高いレベルで維持するためには、日常業務の中で具体的な対策ポイントを意識し、実践することが不可欠です。これらは、食材の受け入れから調理、提供、従業員の健康管理に至るまで、多岐にわたります。
これらのポイントを確実に実行することで、食中毒のリスクを低減し、お客様に安全な食品を提供できる体制を構築することが可能です。また、従業員の意識向上にも繋がり、企業全体の衛生レベルの向上にも繋がります。
具体的な対策ポイントとしては、以下の通りです。
・適切な食材の検品と保管
納品された食材は品温、鮮度、異物混入の有無などを確認します。問題がなければ、適切な温度帯(冷蔵、冷凍、常温)ですぐに保管し、先入れ先出しを徹底します。冷蔵品は5℃以下、冷凍品は-15℃以下での保管が基本です。
・衛生管理の可視化
誰がいつ何を行ったのかを記録し、チェックリストを活用し、衛生管理の実施状況を可視化します。手洗い手順や調理器具の洗浄・消毒手順をマニュアル化し、担当者が変わっても同じレベルの衛生管理を維持することが大切です。
・従業員の衛生状態を保つ
従業員の健康状態を毎日確認し、体調不良者(特に下痢や嘔吐、発熱など)は調理作業に従事させないようにします。また、定期的な検便の実施や、正しい手洗い、清潔な作業着の着用を徹底させます。
・食材を正しく検品する
食材の受け入れ時に、品質、表示(消費期限・賞味期限)、温度、包装の状態などを細かくチェックすることが大切です。疑わしい点があれば、納入業者に確認するか、受け入れを拒否する判断も必要です。
・調理器具の洗浄を徹底する
まな板、包丁、ボール、ザルなどの調理器具は、使用後すぐに洗浄し、必要に応じて熱湯や塩素系漂白剤などで消毒します。特に、生の肉や魚を扱った器具と、その他の食材を扱う器具は使い分けるか、その都度徹底的に洗浄・消毒することが交差汚染を防ぐ上で大切です。
これらの対策ポイントを網羅した衛生管理マニュアルを作成し、定期的に見直しを行うことをおすすめします。また、これらのポイントを従業員と共有し、意識付けを徹底しましょう。
食中毒予防の3原則
食中毒を予防するための最も基本的な考え方が「食中毒予防の3原則」です。これに「持ち込まない」を加えた4つの視点で対策を講じることが、効果的な食中毒予防に繋がります。
・つけない
食中毒の原因となる細菌やウイルスを、食材や手指、調理器具などに「つけない」ようにすることです。具体的には、調理前の丁寧な手洗い、調理器具の洗浄・消毒、生の肉や魚を扱った後の手洗いや器具の交換などが挙げられます。
・増やさない
多くの細菌は10℃~60℃の温度帯で活発に増殖するため、調理済みの食品は速やかに冷却して冷蔵(5℃以下)または冷凍(-15℃以下)で保存し、室温での長時間放置を避けます。
・やっつける
食品や調理器具に付着した細菌やウイルスを加熱や消毒によって殺菌・不活化させます。中心温度75℃で1分間以上の加熱が多くの細菌に対して有効です。また、調理器具は次亜塩素酸ナトリウム溶液などで消毒します。
・持ち込まない
食中毒菌やウイルスを、調理場所に「持ち込まない」という考え方も重要です。従業員が体調不良の際は出勤を控える、外部から持ち込む私物を制限する、ネズミや害虫の侵入を防ぐといった対策が含まれます。
それぞれの原則に対して、自店で具体的にどのような対策ができるかをリストアップし、実行に移しましょう。
食品衛生とHACCPの取り組み
近年、食品衛生管理において国際的に推奨されているのがHACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理です。
日本でも食品衛生法が改正され、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められるようになりました。
HACCPは、原材料の受け入れから製品の出荷までの全工程で、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。これにより、より効果的で効率的な食品安全体制を構築できます。
食品衛生法の改正に伴う主な変更点は以下の通りです。
・「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化
事業者の規模や業種に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかの実施が求められます。
・特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化
事業者が製造・輸入・加工した食品が原因で健康被害が発生した、またはその恐れがある場合、行政への報告が義務付けられました。これにより、迅速な情報共有と被害拡大防止が図られます。
・「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度を導入
安全性が評価された物質のみを使用できる「ポジティブリスト制度」が導入され、より安全な器具や容器包装の使用が促進されます。
・「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設
営業許可が必要な業種が見直されるとともに、一部の業種では新たに営業届出が必要となりました。これにより、行政が事業者をより的確に把握し、必要な指導を行えるようになります。
・食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化
事業者が食品の自主回収を行う場合、その情報を速やかに行政に報告することが義務化されました。これにより、消費者への情報提供が迅速に行われ、健康被害の拡大を防ぎます。
・「輸出入」食品の安全証明の充実
食品の輸出入における衛生管理やHACCPに基づく対応が、相手国との間でよりスムーズに行えるよう、証明書の発行などが整備されました。
事業がHACCPのどの基準に該当するのかを確認し、業界団体が提供している手引書などを参考に、できるところからHACCPの考え方を取り入れた衛生管理を始めてみましょう。現在の衛生管理を見直し、記録をつけ、改善していくという基本的なステップから進めることが大切です。
まとめ
食品衛生は、私たちの健康と安全な食生活を守るために欠かせない取り組みです。食品衛生の目的を理解し、WHOの「5つのカギ」や食中毒予防の「3原則」といった基本的な考え方を日々の生活や業務に取り入れることが大切です。
さらに、HACCPのような体系的な衛生管理手法は、より高度なレベルで食の安全を確保するために役立ちます。食品衛生に関する対策を継続的に実践することにより、食中毒のリスクを低減し、万が一の事故による経済的な損失を防ぐことにも繋がります。食に関わる立場として衛生意識を高め、安全で安心な製品の提供に努めましょう。