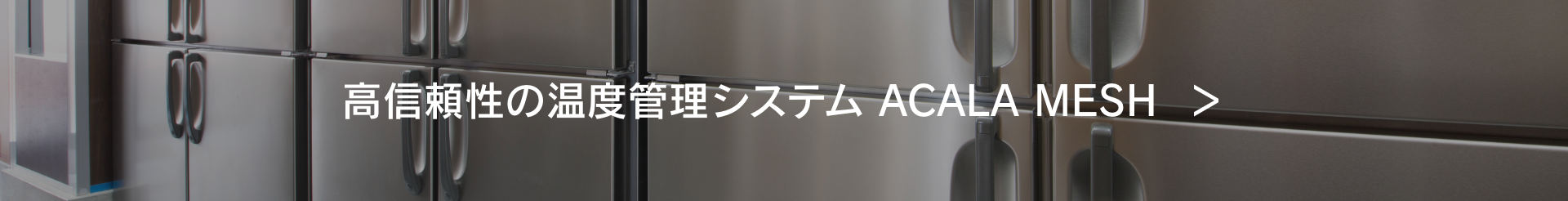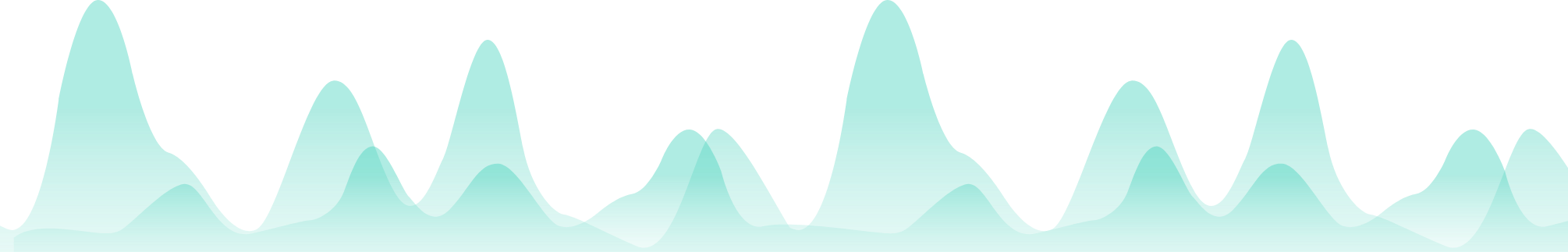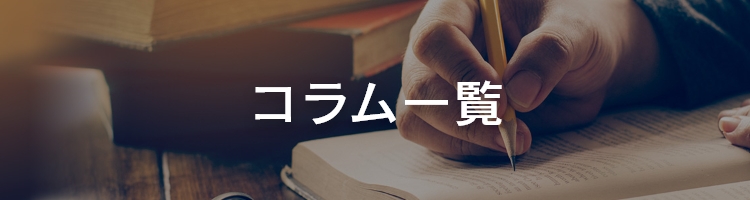
食品製造業に関わる資格の違いを紹介

食品製造業に関する資格の中には、名前がよく似た「食品衛生責任者」と「食品衛生管理者」があります。さらに「衛生管理者」という資格があることをご存じでしょうか? 資格は自身の成長やキャリアアップに有利に働くものですが、適切な資格を選べなければ取得までの努力が無駄になってしまいます。最適な資格を選べるように、食品衛生責任者、食品衛生管理者、衛生責任者の3つの資格の違いを知っておきましょう。
食品製造業の衛生管理に関わる資格
食品製造業に関わる資格に「食品衛生責任者」と「食品衛生管理者」があります。名前はよく似ていますが、2つの資格には明確な違いがあります。両者の違いを理解して、自身に適する資格を選びましょう。
食品衛生責任者
食品衛生責任者の最大の特徴は、食品衛生法に基づき、食品を取り扱うすべての施設で配置が義務付けられていることです。
つまり、飲食店、給食施設、食品工場、食品販売店などの食品に関わる施設や店舗はすべて、食品衛生責任者の資格を持つ者を置かなければなりません。なお、1人が複数の施設や店舗の食品衛生責任者になることはできず、各施設・店舗で1人ずつ食品衛生責任者を配置する必要があります。
食品衛生責任者は、施設や店舗の衛生管理の中心となる存在です。そのため、都道府県知事などが認めた講習会に定期的に参加して、食品衛生に関する知識をアップデートすることが求められます。そして、施設の衛生管理について意見を述べたり、従業員を教育したりして、食中毒などの危害の防止に努めます。
食品衛生責任者の資格を得るためには、自治体や保健所が実施している「養成講習会」を受講しなければなりません。養成講習会では、衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学を計6時間程度で学びます。この講習会を受講すれば、誰でも食品衛生責任者の資格を得られます。
ただし、栄養士、調理師、製菓衛生師などの特定の資格を保持する者は、そのまま施設や店舗の食品衛生責任者になれるため、講習会を受講する必要はありません。
食品衛生管理者
食品衛生管理者は国家資格であり、食品を取り扱う施設の中でも限られた業種のみに配置が義務付けられています。
食品衛生管理者を置かなければならないのは、衛生管理への配慮が特に必要な以下の食品の製造や加工に関わる施設です。
・全粉乳(缶の容量1,400g以下)
・加糖粉乳
・調整粉乳
・食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)
・魚肉ハム
・魚肉ソーセージ
・放射線照射食品
・食用油脂(脱色または脱臭されるもの)
・マーガリン
・ショートニング
・添加物(食品衛生法により規格が定められているもの)
食品衛生管理者の役割は、食品衛生責任者とほぼ同じです。食中毒などの食品危害を防ぐために、施設の衛生管理の中心となり、衛生管理の実施や従業員への教育を行います。
食品衛生管理者の資格取得要件は、食品衛生責任者よりも厳しく設定されています。食品衛生管理者の資格を得るためには、次のいずれかの条件を満たさなければなりません。
・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の資格を持っている
・大学または専門学校で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修了している
・食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了している
・食品衛生管理者を置くべき施設で衛生管理業務に3年以上従事し、都道府県知事が認めた講習会の課程を修了している
なお、食品衛生管理者は食品衛生責任者の役割を果たすことが可能ですが、食品衛生責任者は食品衛生管理者の役割を果たすことはできません。
衛生管理者の資格は食品製造業に関わる?

食品衛生責任者と食品衛生管理者とは別に、「衛生管理者」という資格も存在します。ここからは、衛生管理者の資格の概要と、前述の2つの資格との違いを解説します。
衛生管理者とは
衛生管理者は国家資格であり、常時50人以上の労働者を雇用する事業所への配置が義務付けられています。配置する人数は事業所の規模により決められており、労働者の人数が多くなるほど必要な衛生管理者の数も多くなります。
衛生管理者の役割は、労働者のけがの防止や病気の予防などを担当し、事業所の衛生を管理することです。また、労働者への衛生教育や健康の維持・増進活動にも従事します。
衛生管理者の資格には、第一種と第二種が存在します。第一種は有害業務を含むすべての業種で衛生管理者になれますが、第二種が衛生管理者になれるのは健康リスクが少ない限られた業種のみです。この有害業務とは、健康を害するリスクが高く、適切な管理が必要とされる建設業や製造業、ガス業、運送業などです。
衛生管理者になるためには、試験に合格する必要があります。以下の3つの条件のうち、いずれかを満たしていれば受験できます。
・大学、短大、高等専門学校のいずれかを卒業し、労働衛生の実務経験が1年以上ある
・高校を卒業し、労働衛生の実務経験が3年以上ある
・労働衛生の実務経験が10年以上ある
衛生管理者と食品製造の関係とは
常時50人以上の労働者を雇用している場合、食品を取り扱う施設でも衛生管理者を配置する義務があります。しかし、衛生管理者と食品衛生責任者・食品衛生管理者を置く目的はまったく異なります。
食品衛生責任者・食品衛生管理者の役割は、施設や工場、店舗で取り扱う食品の安全性を確保することです。食品衛生の管理により食中毒などのリスクを低減させて、消費者に安心安全な食を届けることが目的といえます。
一方で、衛生管理者の役割は、事業所で働く労働者の健康を守ることです。労働者が働く環境を改善したり、作業時間や作業方法などを適正化したりして、労働衛生の向上に努めます。健康診断の受診を促すことや健康相談を受けることも、衛生管理者の仕事です。
つまり、食品衛生責任者と食品衛生管理者は食品に関わる資格ですが、衛生管理者は食品に直接関わる資格ではありません。これらの資格は名前がよく似ていますが、混同しないように注意が必要です。
資格取得で気を付けるべきポイント
食品衛生責任者、食品衛生管理者、衛生管理者のように名前や役割が似た資格は少なくありません。そのため、資格取得を検討する際に資格の概要を知ることは重要です。その上で、次の2点についても考えてみましょう。
自分の興味やスキルに合う資格であるか
自分が興味を持てる資格、自分のスキルやキャリアプランに合う資格を選べば、意欲を持って資格勉強に臨めるでしょう。
資格の取得には継続的な勉強が欠かせません。しかし、自分が興味を持てる資格でなければ勉強を続けることは困難です。自分のスキルやキャリアプランに合う資格を選べば、自身の成長につながることがイメージできて、勉強意欲が高まるでしょう。
需要が見込める資格であるか
資格の需要を考慮して、取得を検討することも大切です。
職場で求められる資格、キャリアアップや転職に有利に働く資格であれば、時間やお金をかけて取得する価値があります。反対に、業務やキャリアアップに生かせる資格でなければ取得する意味が薄れ、ただの趣味にとどまってしまいます。
自分が選んだ資格は将来的な需要が見込めるか、取得に要した時間や金額に見合うリターンが得られるか考えてみましょう。
まとめ
食品衛生責任者、食品衛生管理者、衛生管理者の資格の概要と違いについて紹介しました。これらは名前が似ているものの、資格の適用範囲や資格取得者に求められる役割が異なるため、混同しないようにしましょう。
適切な資格を取得すると仕事の幅が広がり、業務量が増えることも考えられます。食品製造業で業務の効率化が必要になったときは、温度管理を自動化できる「ACALA MESH」の導入がおすすめです。
「ACALA MESH」は工場や飲食店の冷蔵・冷凍庫にセンサーを設置することで、温度を自動的に計測、記録できるシステムです。「ACALA MESH」を導入して温度管理業務を効率化し、専門性の高い仕事に集中しましょう。